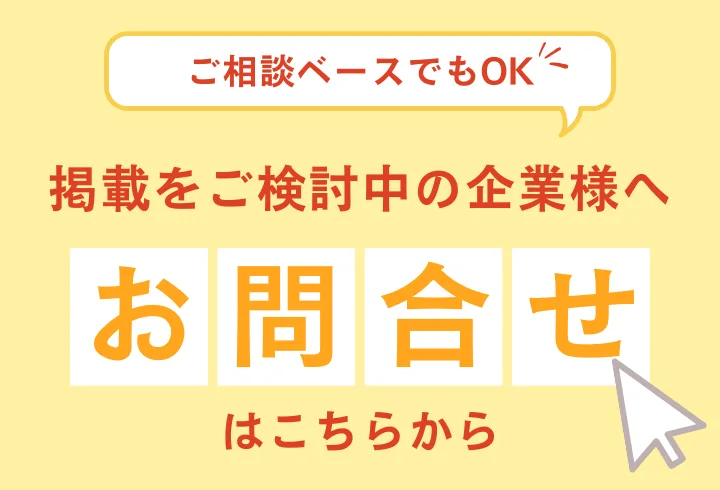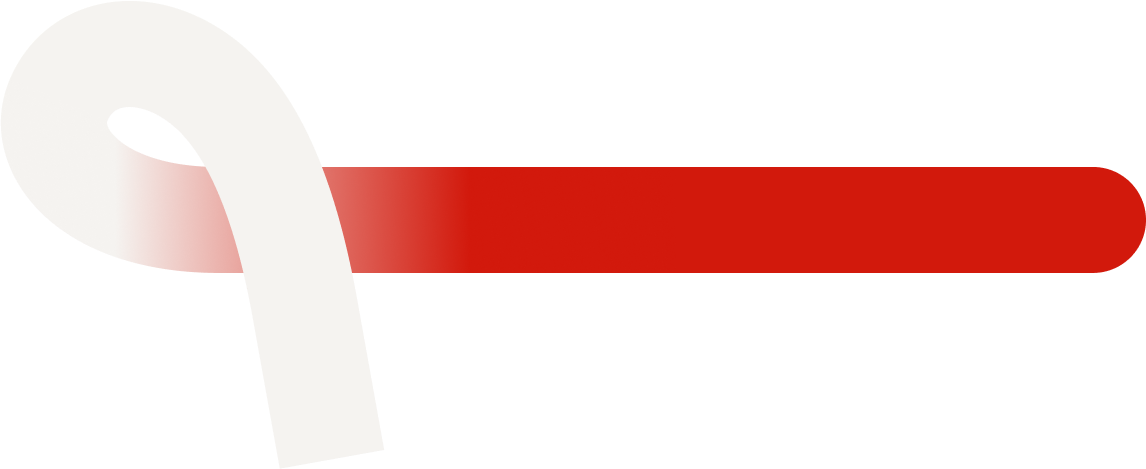「あごが落ちるほど旨いキムチ」というキャッチコピーを聞いたことがあるでしょうか。川崎で生まれたキムチとしてメディアで注目され、一度食べるとそのおいしさの虜になる人が続出しています。今回は、有限会社グリーンフーズあつみの代表取締役社長、渥美和幸社長に「おつけもの慶」の誕生秘話と今後の展望についてお話を伺いました。
川崎のコリアンタウンが、おつけもの慶の原点だった

ーもともとは野菜の卸業をされていたと伺っています。どのような経緯でキムチ作りを始められたのでしょうか?
渥美社長:もともと父が36年前に会社を立ち上げ、近隣の飲食店やスーパーに野菜をお届けする仕事をしていました。川崎にはコリアンタウンがあり、いわゆる在日の方がたくさん住んでいたので、焼肉屋さんやキムチ屋さんに私自身が配達しに行っていたんです。当時は本当に街に活気があって、韓国人が駅前の人通りの多いところでキムチを行商していたりしましたね。
ーその時の体験から、渥美社長にとって「川崎とキムチ」が結びついたということでしょうか?
渥美社長:はい。私にとっては韓国人が街にいて、元気に商売をしているというのは当たり前の日常でした。野菜の卸でいろんなところに配達に行きますから、当時私のような若者が来ると「ちょっと食べていきな」と言って招いてもらって、キムチを頂いたりして(笑)。そしてそのキムチが本当に美味しかったんです。辛いものだから記憶に残りやすかったのかもしれませんが、私にとって「川崎の味=キムチ」になっていったんです。
ーそこからどのような経緯でキムチ作りを始めたのでしょうか?
渥美社長:バブルもはじけて、徐々にコリアンタウンの活気がなくなっていったことがきっかけです。焼肉屋や漬物屋なども世代交代で閉めてしまうところも出始めて、卸先が少しずつ減っていったことに危機感を感じたんです。であれば、自分のところで加工品を作って売ろうという考えになり、自然とキムチが浮かびました。

ー当時キムチ作りは初めてだったと思いますが、どのように製造を行なっていたのでしょうか?
渥美社長:良くしていただいていた焼肉の名店があったのですが、そこが店を閉めることになったんです。そこでキムチ職人として働いていた城野がうちに入ってきてくれたんです。最初は城野には配達の手伝いなんかをしてもらっていたんですが、その店のキムチが美味しかったので、城野と一緒にキムチを作ろうといことで始めました。最初は、お客さんが持っていた住宅街のど真ん中にある10坪のテナントを家賃6万円で貸してくれて、そこでキムチ作りを始めたんです。
丁寧な手作業で、日本人好みの味に
ー製造で気をつけていることなどはありますか?
渥美社長:今でもそうなんですが、おつけもの慶のキムチは全て手作業で作っているんです。オイキムチの大根のカットから手作業です。機械で効率的にやることもできるのですが、そうすると大根の太さによって大きさにバラつきが出てしまう。職人が自ら目で見てカットすることで、大きさを均一にすることができます。キムチの素となるヤンニョムを漬物に練り込むのも手作業です。その方が白菜などの葉の裏にも均等に塗ることができ、味にムラがなくなります。手作りに対するこだわりは創業から変わっていません。あとはヤンニョムの製法ですね。「キムチの素」として販売もしていますが、日本人の好みに合うように果物をブレンドするなどして、甘味とコクが出るように工夫しています。当然、化学調味料などは一切使用していませんので、味わいはかなり深いと思います。

ー私も工場見学をさせていただきましたが、本当に全て手作業で驚きました。そのようにこだわって作られているキムチですが創業当初から順調に売れていったのでしょうか?
渥美社長:最初はなかなか売れませんでした。住宅街の中でポツンとキムチの直売所やってただけですから(笑)。ですが職人の城野の技術と、私の野菜の目利きで本当に美味しいキムチができているという自負はありました。おつけもの慶のキムチは「日本の味」なんです。本場の韓国のキムチは酸味が強く食べづらいと感じる人も多いのですが、我々は日本の食文化の中で独自の成長を遂げて「甘味の中に辛さとコク」がある「日本育ち」のキムチと自負しています。そんな時にたまたまタウンニュースの記事広告の営業が来て、じゃあ出してみようということで記事を書いてもらいました。「住宅街にたった一坪の店」みたいな記事だったかな。それが出てから、店にいくと、店の前でお客さんが待ってたんです。びっくりしました(笑)。看板とのれんだけの小さな店で製造場所も小さいので、行列ができるとすぐに売り切れてしまうんですね。そこから評判になり、行列が耐えない店になりました。
ーそこからは順調に拡大されていったのでしょうか?
渥美社長:実は職人の城野が事故で半年間入院したことがありました。ちょうど行列ができるくらいになった頃で、この頃は病院まで行ってレシピを聞いてなんとかしていましたね。その時にたまたま城野と昔一緒に仕事をしていた西村が来てくれることになり、作ってもらったら同じ味ができたんです。城野も「西村さんならいいよ」と言ってくれ、製造を続けることができました。とはいっても、製造力には限界があるので、行列ができて毎日完売という状態が続いていきました。
「川崎といえば○○」の第一想起を目指して
ー特にブレイクしたと感じたのはいつ頃でしょう?
渥美社長:商店街で「S級キムチグランプリ」というのが開催され、そこで初代のグランプリに選んでいただきました。そこでもう一段知名度が上がったように感じています。その頃から「川崎のキムチを、川崎の味として広めていきたい」という思いが強くなりました。城野が作ったキムチは昔から大好きだったので、これを広めることが自分の使命かもしれないと思うようになっていったんです。
ー徐々に川崎名物として定着をしてきていますよね。
渥美社長:ありがたいことに「かながわの名産100選」に選んでいただくこともできました。2023年10月には川崎大師店がOPENしました。川崎といえばやはり川崎大師が有名なので、そこに出店できたことは嬉しく思います。

ー今後の展望をお聞かせください。
渥美社長:のらぼう菜という野菜が、川崎中心に生産されているのですが、こういった地元の野菜などを使ったキムチ作りは推進していきたいですね。やはり私自身、川崎で生まれ育ち、コリアンタウンと深く関わって生きてきたという実感があります。祖母が八百屋をやっていたのですが、空襲があったときに韓国人の方が最初に助けてくれたそうなんです。祖母からは一切差別をするなと言われて育ちました。キムチを通して川崎に貢献していくというのは、私にとってすごく自然なことなんです。いずれ「川崎といえばおつけもの慶」と最初に思い出してもらえるような存在にしていきたいと思っています。
編集後記
私もよくキムチを食べるのですが、おつけもの慶のキムチは本当に甘味とコクがあって、日本人の味覚にフィットします。とにかくご飯に合うんです。今回、取材を通して感じたのは「この時代に、川崎で生まれ、川崎で野菜卸の息子として育った渥美社長だからこそ、このキムチが生まれたのだな」という必然性です。日本と韓国の文化が融合する場所だった川崎コリアンタウンから、日本人好みの味のキムチが生まれ、川崎の野菜を取り入れて全国に広がっていく。そう考えるとワクワクしますし、おつけもの慶がより広まっていくことが楽しみになります。おつけもの慶のキムチはオンラインショップで購入ができますので、気になった方はぜひ試してみてください。
ご紹介
Profile

有限会社グリーンフーズあつみ
代表取締役