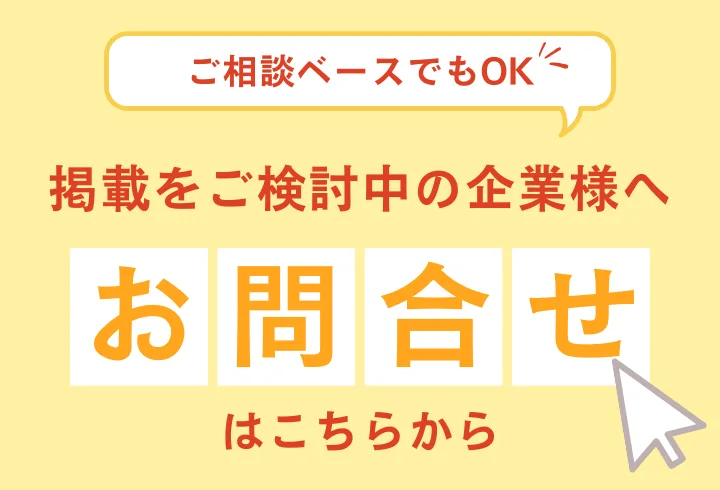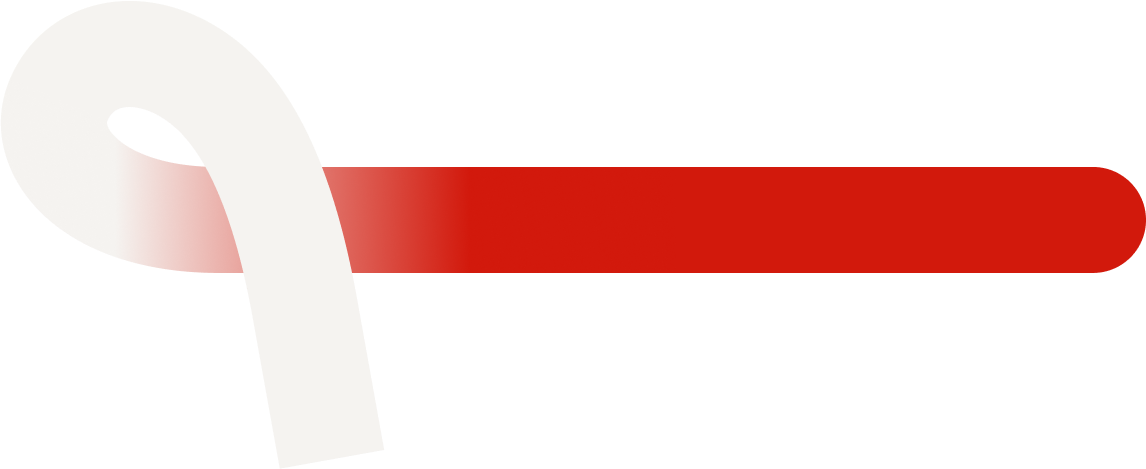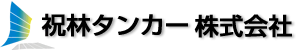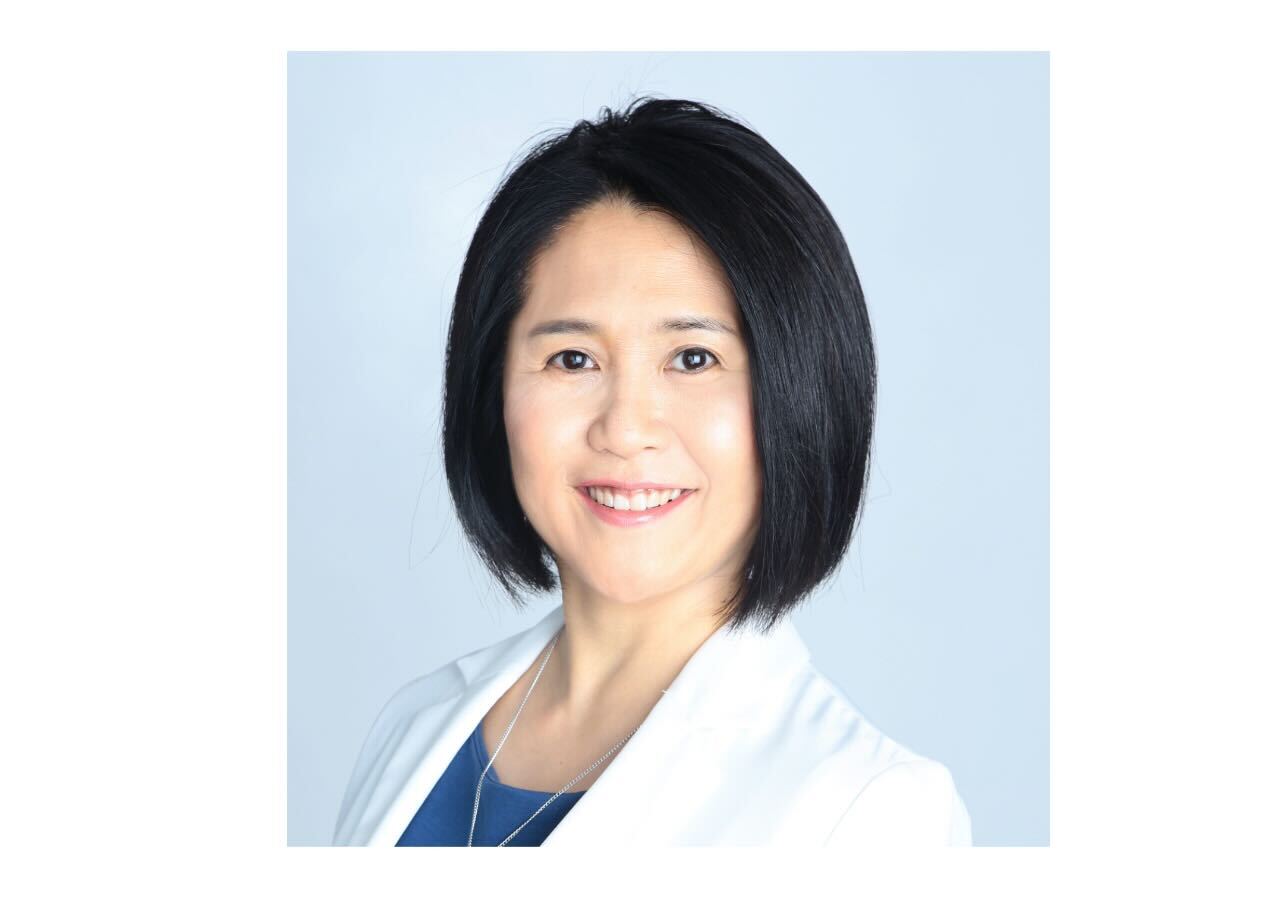「日本の経済を支える“見えないインフラ”こそ内航海運です」と語るのは、
山口県下関市に拠点を置く 祝林タンカー株式会社 代表取締役専務・林俊資さん。
創業63年を迎える同社は、ガソリンや軽油、ジェット燃料などを全国に届ける使命を担ってきました。林さんは富士フイルムで製造技術者として勤務した後、父親からの声を受けて家業に戻った異色のキャリアの持ち主。今回は祝林タンカーの歴史と社会的役割、そして海の上で働く船員たちの知られざる暮らしについて伺いました。
目次
創業の原点 ― 山口県漁協から始まった「海から燃料を届ける」仕事
石塚: まずは会社の歴史を教えていただけますか?
林: 創業は昭和37年(1962年)、現在で第63期になります。山口県漁協の中で漁船に油を売るところからスタートしました。
当時は「漁連石油」という会社があり、自分たちの船で漁船へ直接給油する――まさに“海のガソリンスタンド”が原点です。
その後、燃料需要の増加にともない、横浜の上野運輸商会(現・上野トランステック)様からガソリン輸送の依頼を受け、全国への燃料輸送事業へと拡大しました。
以来60年以上、内航海運を通じて日本のエネルギーを支え続けています。
林俊資さんの歩み ― 富士フイルムで学んだ技術と経営の視点
石塚: 林さんご自身はどのような経緯で家業に戻られたのですか?
林: 中高は長崎の寮生活、大学と大学院は福岡で学び、富士フイルムに製造技術者として入社しました。5年半勤める中で、「失敗しても成功するまでやり続ければ、それは失敗ではない」という考え方を学びました。課題をデータで積み上げ、成果を出す――その姿勢は今の仕事にも活きています。
石塚: 異業種からの転身ですね。
林: 結婚と出産を機に帰郷しました。いきなり経営に入るのではなく、まずオペレーター系のグループ会社に出向入社しました。内航・外航の代理店業務、VLCC(大型原油タンカー)の接岸管理などを担当し、2年半かけて港湾運用や荷役の実務を徹底的に学びました。
この経験が、「現場を理解する経営者」としての基盤になっています。

ガソリン輸送の仕組み ― “内航タンカー”がつなぐエネルギーの血流
石塚: ガソリンはどのように全国に届くのでしょうか?流れを教えていただけますか?
林: はじめに、原油は中東(サウジアラビア・UAEなど)からVLCCで日本に届き、国内の製油所で精製されます。そこから私たち内航タンカーがガソリンや軽油を各地の油槽所へ運び、タンクローリーでスタンドに配送します。
たとえば、広島で積み込んだ燃料を18時間かけて長崎へ運び、そこから陸送されて市内のスタンドへ。
この海上輸送が止まれば、ガソリンスタンドが空になり、物流も経済も止まってしまいます。
石塚: まさに社会を支える仕事ですね。
林: そうです。内航海運は、日本の生活を動かす“社会インフラ”です。
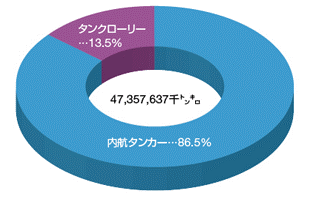
86.5%と圧倒的なシェアを占めている
船員の働き方と暮らし ― 「3か月乗船・1か月休暇」、Starlinkで変わる海上生活
石塚: 船員の働き方について教えてください。
林: 基本は「3か月乗船・1か月休暇」になります。働き方改革もあり、週1日の休みも確保され、健康的に働ける環境になっています。
また、船種によっては日帰り運航型もあります。朝出港して夕方帰港、家庭を持つ人も働きやすいスタイルです。
船内は全員個室、食堂とシェフ付き。さらにStarlink(衛星通信)を導入しており、
船員は映画を観たりオンラインゲームをしたりと、快適な生活が可能です。
通信費・光熱費・食費はすべて会社負担。生活費がほぼゼロのため、3か月で100万円貯金する若手もいますね。
石塚: それはすごいですね。
林: “3か月働いて1か月まるっと休む”――まさに大人の夏休みです。ただ、小所帯なので人間関係は濃く、協調性が何より大事ですね。

内航海運の課題と使命 ― 船員不足が社会を止める
石塚: 内航海運業界が抱える課題はありますか?
林: 一番の課題は人材不足です。船員がいなければ新しい船も動かせず、結果的に社会インフラが滞ります。
実際、羽田空港の増便が見送られた理由のひとつが、「ジェット燃料を運ぶ船が足りない」ことでした。
また、北陸など製油所がない地域では、海上輸送が生命線。需要はあるのに、船員がいなければ供給が追いつかないんですね。
新造船を発注しても就航まで約4年かかるため、人材確保が日本経済全体の課題になっています。
石塚:なるほど。内航海運の重要性が伝わります。
林: ええ。“船員がいなければ飛行機も車も動かない”。
それが現実です。だからこそ誇りを持って働ける仕事だと思います。
未来への航路 ― 未経験から挑戦できる仕組みと、未来の船員へのメッセージ
石塚: 条件面や働く環境がとても魅力的に映りますが、実際に未経験者でも船員を目指せますか?
林: はい。広島の海事系養成校(半年課程)で基礎資格を取れば、海技免状(国家資格)を取得できます。乗船経験を積めば、1年ほどで上位資格も目指せます。
費用は約200万円ですが、そのうち120万円は奨学金制度で貸与可能です。
経済的負担を抑えてスタートできます。
また、当社は長期航海型・通勤型など複数の船型を保有しており、ライフステージに合わせて働き方を選べます。2026年10月には6,000kL型の新造船が竣工予定です。
石塚: ありがとうございます。最後に、船員志望の方やそのご家族の方々へのメッセージをお願いします。
林: 海で働くことに不安を感じる方も多いと思います。しかし、祝林タンカーでは安全教育とサポート体制を徹底しています。
作業中の安全対策はもちろん、体調不良やトラブルがあっても、陸上の運航管理スタッフが即座に対応できる体制を整えています。海上と陸上が常に連携し、「一人にしない職場」を目指しています。
海で得られる経験は、たくましさと自信を育て、人生の財産になります。
仲間と支え合いながら、社会のエネルギーを動かす――その誇りを感じてほしいと思っています。
私たちは、「乗りたくなる会社」を目指し続けます。
給与や休暇だけでなく、安心・安全・誇りのすべてが揃う職場として、次の世代へこの仕事の魅力をつないでいきたいと思います。
編集後記
対談を通じて強く印象に残ったのは、祝林タンカーの「人を大切にする姿勢」でした。
3か月働いて1か月休むという明確なサイクル、生活費がほとんどかからない船上での暮らし、
そして専属シェフの食事やStarlinkによる高速通信環境。
それらは単なる福利厚生ではなく、現場で働く人を支えるための設計思想だと感じました。
船の上では、厳しさと非日常が常に隣り合わせです。しかし同時に、陸では得られない充実感や達成感があります。それを実感できるのは、海で働く人だけの特権かもしれません。
林さんが語っていた「飛行機の増便すら船員不足が影響している」という言葉は、
内航海運の存在の大きさを象徴していました。
ガソリンも、ジェット燃料も、すべて海が運んでいる――。
普段は見えない場所で、日本の生活と経済を支えているのが、この業界の本質だと改めて感じます。
祝林タンカーが担っているのは、単なる輸送事業ではありません。
社会インフラを守り、次の世代へつなぐという使命そのものです。
「インフラを支える誇り」という林さんの言葉には、経営理念を超えた現場の実感が込められていました。
静かに、しかし確かな使命感をもって。
祝林タンカーはこれからも、日本の海を走り続けていくのだと思います。
ご紹介
Profile

株式会社祝林タンカー
代表取締役 専務
山口県下関市に拠点を置く祝林タンカー株式会社の代表取締役専務。
大学卒業後、富士フイルムで製造技術者として勤務したのち、家業である海運業に戻る。創業60年以上の歴史を持つ祝林タンカーにおいて、安全運航と船員教育を軸に事業を牽引。
ガソリン・軽油・ジェット燃料など、国内のエネルギー輸送を担い、日本の社会インフラを支える役割を果たしている。近年はStarlink導入など労働環境の改善にも注力し、次世代の船員育成と業界の持続性を見据えた取り組みを推進している。

株式会社ウェブリカ
代表取締役
新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。 ■編集長インタビュー https://chiiki-shikisai.com/webrica-ishizukanaoki/