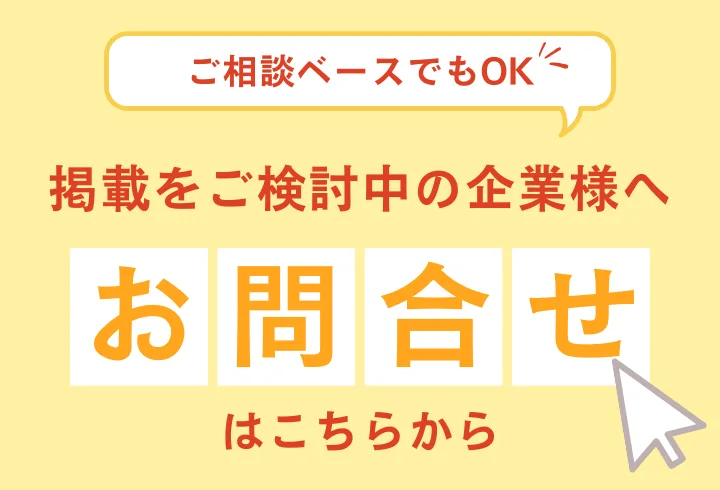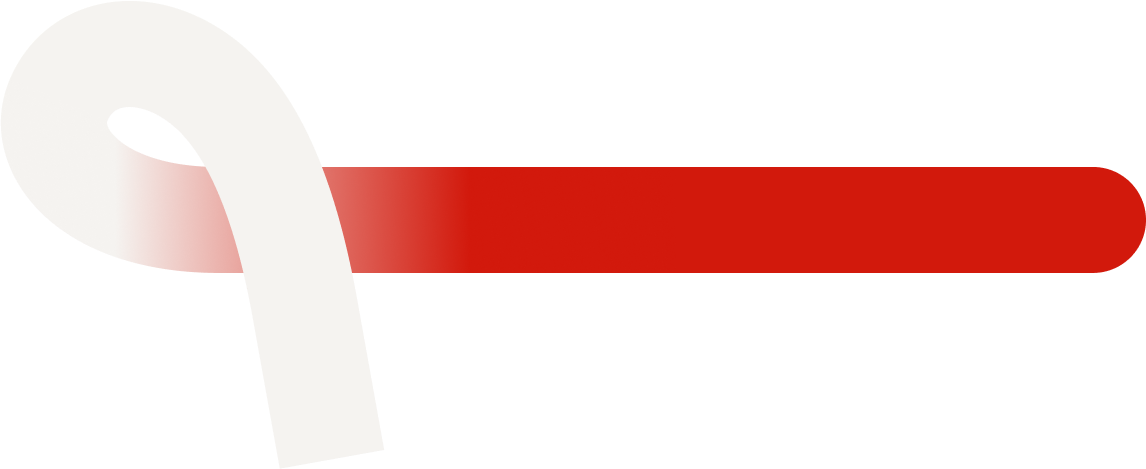大分県に本社を置く株式会社ダイナンは、1972年創業の縫製メーカー。ミシン2台から始まった家業は、いまや100名を超えるスタッフを抱える企業へと成長しました。父の背中を見て育った二代目・但馬史晴さんは、異業種から家業に戻り、現在は代表取締役として新たな挑戦を続けています。
「縫製には、魔法の力がある」。その言葉に込められた想いとは——。地域に根ざし、人の手で布を形に変え続けてきたダイナンの歩みと、次の50年への展望を伺いました。
目次
ミシン2台から始まったダイナンの原点
石塚:まずは、株式会社ダイナンの歴史について教えてください。創業はいつ頃だったのでしょうか?
但馬さん:1972年の創業で、現在でちょうど54期目になります。創業者は父で、高校を卒業してすぐ大阪の繊維関係の仕事に就き、そこで生地や洋服の販売、卸などを経験しました。その後、家族の事情で地元・大分に戻り、知人の勧めで縫製を始めたのがきっかけです。実家を改装して、ミシン2台からスタートしたんです。
石塚:ミシン2台から、いまでは100人規模に。すごい成長ですね。
但馬さん:はい。最盛期には200名を超える従業員がいました。高度経済成長期で、国内の縫製工場がどんどん拡大していた時代です。創業当初は子ども服やボトムスなどの量産が中心でしたね。
エンジニアから縫製業へ-異業種転身の決断
石塚:但馬さんご自身は、最初から家業を継ぐつもりだったのですか?
但馬さん:いえ、まったく考えていませんでした。大学では工学部を出て、半導体関連の会社に就職しました。光通信用半導体製造のエンジニアとして働いていたんです。ところが、ITバブルが弾けた2000年代初頭に会社の業績が悪化してしまって——。
石塚:まさにITバブル崩壊の時期ですね。
但馬さん:はい。その時に、自分のキャリアを見つめ直す機会がありました。安定していたはずの職場が揺らぎ、ふと「地元で何かできないか」と考えたんです。そして、父が経営するダイナンを手伝うことを決め、2003年に入社しました。
石塚:まったく別業界への転身だったわけですね。最初は戸惑いも多かったのではないでしょうか?
但馬さん:そうですね。最初は正直、縫製の世界は右も左も分かりませんでした。でも、現場の人たちの手仕事の精度や集中力を見て、「ものづくりの本質は一緒だ」と感じました。半導体も縫製も、最終的には“人の技術”で支えられていると。
中国駐在で学んだ「人を動かす力」
石塚:入社後はどのようなお仕事を?
但馬さん:当時、ダイナンは中国にも生産拠点を持っていました。私はそこに派遣され、現地法人の生産管理と経営全般を担当しました。入社して1年半ほどでの赴任でしたが、約5年間、中国で働きました。
石塚:それは大変な経験ですね。苦労された点は多かったのではないでしょうか?
但馬さん:やはり“人を動かす”ことの難しさを感じました。文化も価値観も違う中で、どうチームをまとめるか。言葉以上に、誠実さや一貫性が試される環境でした。毎日が勉強で、同時に人間力を磨かれた時間でした。
代表就任-父からのバトンと視点の変化
石塚:代表取締役に就任されたのはいつですか?
但馬さん:2009年の3月です。中国から帰国して約1年後でした。当時はまだ父が健在でしたが、年齢的なこともあり、そろそろ世代交代のタイミングだと判断されました。私としても、現場と経営の両方を学んだ時期で、覚悟を決めて引き継ぎました。
石塚:父から経営を引き継ぐというのは、大きな節目ですよね。
但馬さん:はい。父は職人気質で、現場の声を最も重んじる人でした。代表になって初めて、「会社を背負う」という責任の重さを感じましたね。数字だけでなく、人の生活や成長を預かっている。その実感が、経営者としての視野を広げてくれました。

“挑戦する工場”が築く技術と文化
石塚:それから現場の雰囲気も変わりましたか?
但馬さん:少しずつ変わってきたと思います。うちの会社は、難しい仕事にも「やってみよう」と挑戦する風土があります。以前、あるブランドから非常に難易度の高いサンプル製作を依頼されたことがありました。袖のパーツがボロボロになるまで試作を繰り返し、最終的に「ここまでやるなら量産も任せられる」と言ってもらえたんです。
石塚:それは中々凄いことですよね。
但馬さん:ええ。失敗を恐れず、やれるところまでやってみる。そういう姿勢が、ダイナンの技術の進化を支えてきたと思います。

「縫製には魔法の力がある」——理念とリブランディング
石塚:ダイナンでは「縫製には魔法の力がある」というクレドを掲げていると伺いました。とても印象的な言葉です。
但馬さん:ありがとうございます。これは50周年を迎えるにあたって、私たちが自分たちの仕事の本質をもう一度見つめ直そうとした時に生まれた言葉なんです。縫製というのは、単に服を作るだけではなく、人の心を動かす力があると思っています。
石塚:“魔法の力”とは、具体的にどういう意味でしょう?
但馬さん:洋服には、目に見えないエネルギーがあります。たとえば、晴れの日にお気に入りの服を着ると気持ちが上がったり、誰かに褒められると少し自信が湧いたり。そういう「感情を生む力」を私たちは“魔法”と呼んでいます。だからこそ、1枚の服を縫うにも真剣なんです。


働く人々の物語——若手とベテランが繋ぐ現場
石塚:従業員はどういった方がいらっしゃいますか?
但馬さん:高校を卒業したばかりの若手から、80代のベテランまで幅広いです。40年以上勤めてくれている方もいます。縫製は技術職なので、経験と感覚が大切なんです。ベテランの方々が若い人に惜しみなく技を教え、チームとして継承しています。
石塚:それは素晴らしい環境ですね。人材の確保は難しくありませんか?
但馬さん:もちろん、今はどの業界も人材確保が大変です。だからこそ、会社の中を見せて、縫製の仕事の面白さを発信しています。「ものづくりが好き」「服が好き」という人に、うちの現場を見てほしい。縫製は機械ではなく“人の手”で支えられているということを知ってほしいんです。

次の50年へ-社員とともに描く未来
石塚:ダイナンの今後の展望について教えてください。
但馬さん:将来的には、自社ブランドを立ち上げたいと思っています。これまで培った技術を生かして、社員みんなでコンセプトから形にしていくようなブランドを。まだ構想段階ですが、「挑戦する工場」の新しい姿として挑みたいですね。
石塚:まさに次の50年への一歩ですね。
但馬さん:はい。縫製業界は「斜陽産業」と言われることもありますが、私はそう思っていません。服は人の暮らしに欠かせないもの。メイド・イン・ジャパンの品質と精神を大切にしながら、地域の人々とともに新しい価値を作っていきたいと思っています。

編集後記
今回の制作を通して感じたのは、但馬史晴さんの言葉の一つひとつに、“静かな情熱”が宿っているということでした。「縫製には魔法の力がある」という言葉は比喩ではなく、服づくりが人の感情に寄り添い、人生を彩る力を持つという実感から生まれたものだと思います。
現在、国内のアパレル生産は減少を続けています。しかし、ダイナンの工場では、若手からベテランまでが一緒になり、真剣にミシンに向かう姿がありました。
その光景には、“日本のものづくり文化”が確かに息づいています。
効率では測れない価値を信じ、手のぬくもりを伝える仕事を続ける。
その積み重ねが、これからの時代に必要とされる“本当のものづくり”なのだと思います。
ダイナンの次の50年が、どんな新しい服と物語を生み出していくのか。
その未来を心から楽しみにしています。
ご紹介
Profile

株式会社ダイナン
代表取締役
大分市を拠点に、戦後から続く縫製業を2代目として継承する。
創業以来「ご縁を大切にする」精神を受け継ぎ、国内縫製ならではの小ロット・高品質対応を強みに事業を展開。
ブランドや事業者のものづくりを支援する「縫製のおてつだい」など、新たな挑戦にも取り組んでいる。海外生産が主流となる厳しい環境の中でも「人の手が生み出す魔法の力」を信じ、社員を家族同然と考えながら、人材育成と働きやすい環境づくりに力を注いでいる。

株式会社ウェブリカ
代表取締役
新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。
腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。
地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。