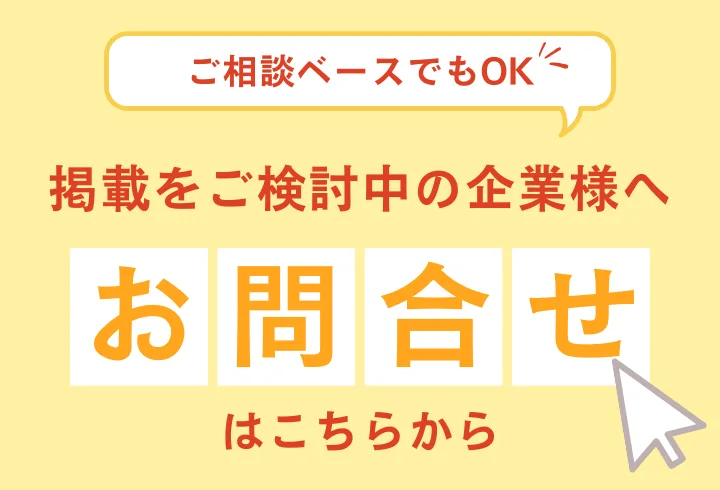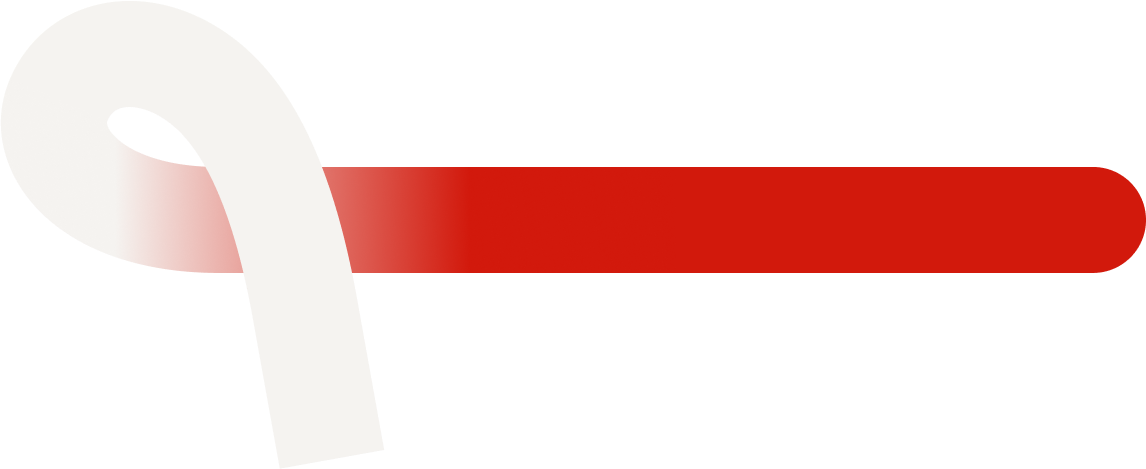「患者さんの想いに寄り添いたい」という原体験から設立された「株式会社ナーシング」。
看護師時代の経験から企業に至るまでと、現在と今後のビジョンについて、代表取締役の鈴木由紀子さんにお話を伺いました。
目次
「患者さんの想いに寄り添いたい」原体験から生まれたサービス
── 元々看護師のお仕事をされていたそうですが、医療従事者から会社を立ち上げたきっかけを教えていただけますか。
鈴木さん:私は、新卒から看護師として病院で働いていました。勤務していた病院は、いわゆる「急性期病院」で、病気を発症して健康状態が急激に悪化した患者さんを受け入れており、私は消化器内科に所属していました。そこで、患者さんを看取ることがしばしばあったのですが、「これでよかったのか」と感じることが多くあったんです。

死を目前にした患者さんは、家族や周囲の方に残したい想いや伝えたいことがあると思います。でも、実際の医療現場では、マンパワー不足などさまざまな理由で難しい現状がありました。私は、その想いに寄り添えなかったことに対して罪悪感を感じるようになり、同時に患者さんに寄り添える施設を作りたいと思うようになりました。
── そうだったんですね。病院勤務での原体験がきっかけとのことですが、現在の事業のメインは障害福祉領域かと思います。医療ではなく、こちらの業界で立ち上げたのはなぜですか?
鈴木さん:当初は看取りの施設をやりたいと思っていて、そのためには医療業界全体の人材育成や教育体制が必要だと考えました。病院での勤務はテクニカルなスキルは伸びますが、ヒューマンスキルの教育はされていない場合が多いんです。これは私自身にも言えることで、いかに小さい人間だったかを感じて、すごく反省しましたね。
障害福祉の領域で立ち上げたのには、いくつか理由がありますが、たまたま知人の経営者の方とお話したことがきっかけです。その後、自分でも調べたら、この業界に対してすごく危機感を感じました。
障害を持つ子どもたちが必要な療育を受けて、社会に参画できるようにする支援がまだまだ整っていない、その環境を早く作らないといけないと思ったんです。子どもの成長は待ってくれないですし、「子どもの頃に適切な教育やトレーニングなどを受けられていれば、その後の社会生活で生きやすくなったのに」ということをできる限りなくしたいと考えています。
福祉や保育、教育の分野は、もっとやれることがあると思いますし、今やらないと業界全体の質が下がってしまうと危惧しています。業界課題を放っておくと大変なことになるという思いから、ナーシングを立ち上げました。今は児童の課題(伸び代)に合わせた福祉施設の展開を軸に、高等学院での教育事業や大人向け事業などを組み合わせ、「ナーシングモデル」として事業展開の幅を広げています。
また、この業界で起業した理由の一つとして、収支がわかりやすいということもあげられます。売り上げと経費、利益がわかりやすく、仕組化しやすいという業界自体の強みもありますね。
── 立ち上げの際、大変だったことや苦労されたことはありましたか?
鈴木さん:看護師時代は大きな病院で働いていたので、ゼロイチで何かを作ったことはありませんでしたし、お金も信用もない状態だったので、今思えば大変でしたね。
ただ、業界課題を解決したいと周囲に話していく中で、共感して出資してくださる方や協力してくださる方が何人かいらっしゃり、それは本当にありがたかったです。
放課後等デイサービスを中心に障害福祉事業を展開
── 現在の事業について教えていただけますか?
鈴木さん:現在は、放課後等デイサービスや児童発達支援、生活介護、就労支援など、複数の事業を展開しており、特に障害児支援に注力しています。具体的には、放課後等デイサービスと児童発達支援が中心で、全体の65%程度を占めています。残りの35%で大人向けの事業や教育事業などを展開しています。現在運営している拠点は3箇所で、全て愛知県内です。
放課後等デイサービスと児童発達支援は、障害特性を持った子どもに対する発達支援や、保護者支援等を行うサービスです。弊社の施設では、知的障害や発達障害(神経発達症)などを抱える幼稚園・保育園児や小学生がほとんどですね。
障害特性を抱える子どもは、個人差はありますが、大なり小なり社会性に課題があります。例えば、ADHDは、注意欠如や多動、衝動性など、ASD(自閉スペクトラム症)はコミュニケーションやこだわりなどについてです。
障害特性を持つ人は、脳の構造が違うと言われているので、それを踏まえて社会や集団で生きていくためのソーシャルスキルトレーニングを実施しています。内容は、その子の個性や課題、療育のフェーズなどによって、子ども一人一人に合わせて変えています。
── 具体的にはどのような療育が受けられるのですか?
鈴木さん:例えばですが、ある小学生の子どもには、「こんなときどうする?」など場面を想定し、意見を出したり対応を考えたりします。あと、距離が近すぎる子や言葉での理解が難しい子だと、「『前へならえ』くらいの距離のパーソナルスペースをあけよう」など具体的に教えることもあります。
また、どれだけ素晴らしいことを大人が伝えたとしても、その大人自身が実践できていなければ、当然子どもは学びを受け取れません。背中を見られている意識を忘れずに、我々が意識的にチーム全員で、気持ちの良いものの貸し借りや「ありがとう」「ごめんね」などのコミュニケーションを実践して、モデリング学習を促しています。
私たちの療育は、生きやすくなるためのスキル獲得を目的としています。早く支援をうけることで、その後の人生がもっと生きやすくなるので、子ども一人ひとりにあった支援を受けることがスタンダードになってほしいと思います。
チーム力が高く同じ価値観を共有しているナーシングのメンバー
── 会社の特徴について教えていただけますか。
鈴木さん:ナーシンググループ全体で40名程の従業員がおり、9割近くがフルタイム勤務の仲間です。特徴は、チーム力が高く、全員が同じ方向を向いて働いているところです。業界未経験者が7割と比較的多く在籍しており、経験の有無によらず、双方が気付き、学び合う文化ができていると思います。
ナーシングには、会社が大事にしている価値観や目指している世界観に共感する人たちが集まっています。メンバーは今まで働いてきた思いや葛藤をそれぞれ持っていて、他社ではできなかったけどナーシングなら夢を描けたという人や、個人では達成することが難しくてもチームや会社ならできると考えて働いている人もいます。
皆さん、視座が高くて向上心があって気持ちのいい人が多いので、「こんなふうにやりたい」と意見を出してくれる人がたくさんいて、メンバーには恵まれていると思います。
── ナーシングならではの強みや働くメリットはありますか?
鈴木さん:まず、やりたいことが叶えやすい環境があります。
私たちは「希望の光であり続ける」という存在意義(MISSION)を体現し続ける先に、「医療・介護・福祉・保育・教育業界のNew Standardになる」というVISIONを掲げています。業界の質の底上げや価値向上を目指し、ALLWINの世界を本気で体現しようと、チームで挑戦しています。論語と算盤が成り立ち、MVVに基づき「我々がやるべきことなのか?我々だからできることなのか?を検討した先に、ALLWINの未来が見えれば、積極的に新規事業に挑戦していきます。
例えば、高等学院の事業は、従業員の発案がきっかけでできた教育施設です。挑戦意欲や向上心のある方は、自分のやりたいことを具現化しやすい環境だと思います。
また、働きやすさとやりがい、待遇面などの環境についても従業員が作ってくれていて、2024年度は働きがいのある会社ランキング(小規模企業)でトップ100に入りました。実は、福祉の業界の会社が入ることはほとんどないんです。その他では、人事評価制度により、自身が会社から何を期待されているのかが明確になっているため、抜擢人事や昇格昇進のスピードが速いことも特徴として挙げられます。
教育体制としては、各店舗でのOJTや勉強会、年数回の全社研修もありますので、未経験の方も大歓迎しています。働きがいには、働きやすさも含まれていますので、公私共に活用できる福利厚生サービスを導入しています。
── 現在、採用に力を入れているそうですが、どのような方と一緒に働きたいですか?
鈴木さん:ナーシングのVALUESに共感し、体現してくださる方にはぜひ来てほしいですね!
自分ができそうか?よりも自分がこうなりたいか、を大事にしていますので、「成長意欲はあるけど、自信ないかも」と感じる方には、気軽な形でナーシングの仲間にオンラインで質問したり、等身大のリアルな声を聞いてもらえる機会を設けています。
VALUESには、①信頼と敬意②真摯さ③感謝④向上心⑤リーダーシップ⑥一致団結の6項目を掲げています。業務中に判断に困ったときは、VALUESに基づいて判断してもらっていて、この基準があることで、メンバーが安心して働けると考えています。
VALUESを大事にしている人たちと一緒に働けたらいいな」と少しでも感じていただけた方には、ぜひ一度、お気軽にホームページから問い合わせてもらえたら、とっても嬉しいです。
福祉・保育・教育・医療・介護の各分野で順次サービスを予定
── 今後の事業展開について教えてください。
鈴木さん:まず、障害福祉の事業では、障害をお持ちの方を取りまく地域社会に対してのアプローチを進めていきたいですね。
例えば、会社や公的機関などで働いてる障害特性をお持ちの方に対して、かかわり方や支援方法について悩んだり手をこまねいてたりする場所や組織は、まだたくさんあると思います。そういった場所に対して、医療従事者や専門家が多数所属している弊社だからできることをどんどん形にしていきたいです。
また、教育と福祉の垣根を下げたいとも考えています。
具体的には、愛知県の公立の小・中学校の先生を対象に無料セミナーを年に一回実施しています。障害特性を持つ子供たちに対して、何とかしてあげたいけどどうしていいかわからないと悩んでる学校の先生に向けたセミナーです。専門分野の講師の先生をお呼びし、弊社従業員も同じセミナーを受けています。

教育分野について、高等学院の事業は数年先に学校法人化を視野に入れていて、ますます幅が広がっていく予定です。
店舗展開については、現在は愛知県内のみですが、今後はまだ業界にないであろう大型の複合施設や、全国へ展開していくことを予定しており、現在はその準備をすすめています。
医療・介護・福祉・保育・教育の分野で優先順位や従業員の声を考慮しながら、さまざまに事業を実施していく予定で、それぞれマネタイズできるよう設計しています。最終的には、看取りの施設をやれたら嬉しいですが、夢を描きながら一歩一歩進んでいきます。
編集後記
看護師時代から一貫して「相手に寄り添う」姿勢を持ち、自ら体現されてきたことが強く印象に残るインタビューでした。また、熱い想いを持ちながらも、社会的価値とマネタイズの両立を意識されている点も印象的でした。
今後のビジネスをさらに発展させ、支援の輪や幅が広がっていくことを願っています。
ご紹介
Profile

株式会社ナーシング
代表取締役
愛知県名古屋市の大学病院で、7年間看護師として勤務。
もっと患者さんやご家族の想いを深く学びたいと思い、在職中に通信大学へ編入学、心理学学士を取得。
根拠に基づく療育の提供、スキルと同時に人間性の向上を目指す人材育成、医療福祉業界の労働環境の高水準化など、医療福祉事業での「もっとできることがある」を形にすべく、満を時して2020年5月に株式会社ナーシングを設立。