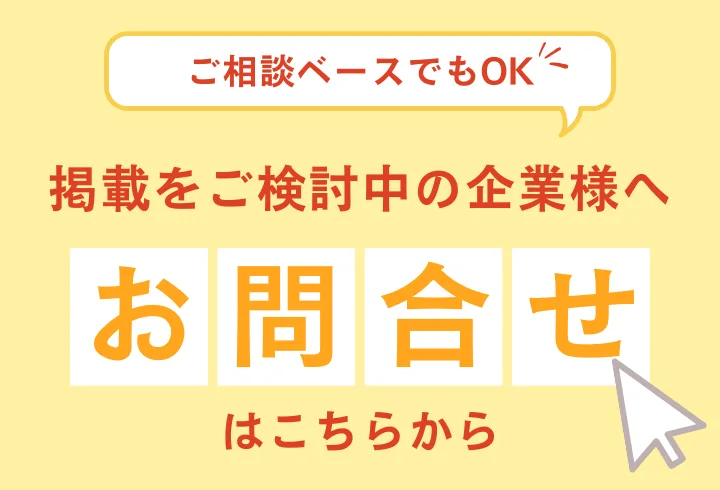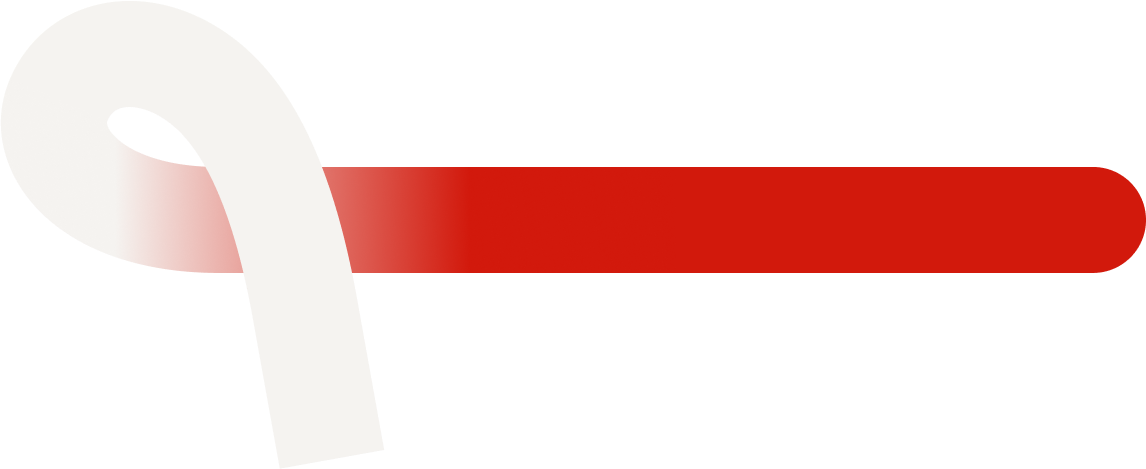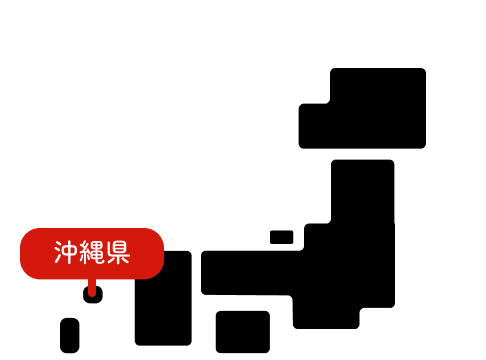1949年創業の請福酒造は、漢那さんが3代目として石垣島で酒造りをされています。酒造店では珍しいバリエーションの多さが魅力的です。今回はその中から歴史的背景が強く、地元・石垣島と密接な関わりを持つ芋酒・IMUGE.の商品の魅力についてお話を伺ってきました。
目次
戦後間もない時期に創業した会社
—会社の創業はどういった経緯だったのでしょうか?
漢那さん:請福酒造は私の祖父が戦後から帰ってきて、創業した会社です。その当時・石垣島はアメリカのもので法律も全く違うものでしたから、日本だと酒造は免許制のところがそうではなく新規でなんでもやれる時代でした。元々、祖父は農業をやってたらしいんですが、新規で泡盛を作る人が増えていたので流れに乗って、酒造りを始めたと聞いています。その当時泡盛メーカーは47社くらいだったかなと。ただ、お米をベースに作るとしても、沖縄では米の価値が高かったので、米が使えずいろんなものを使って酒造りをしていたと聞いています。やがて、品質的にも淘汰されて泡盛メーカーも減っていきました。
—請福酒造が淘汰されずに生き残れた理由はどこにあったのでしょうか?
漢那さん:技術力だと思います。免許制じゃなかったので、酒造りの入口は広かったですけど、技術があると安定的に美味しいお酒を作れるので、まともにお酒を作れるところが残ってきたんだと思っています。
—家業は初めから継ごうと思っていたのでしょうか?
漢那さん:継ごうと思っていました。大学卒業後から実家に戻って家業を継いでいましたが、30前半の時に突然「来月から社長やりな。」って言われて代替わりした形です。もの作りや会社経営は私の性に合っていたので、なること自体のハードルは高くありませんでした。
商品作りはマラソンと一緒
—漢那さんが代替わりをされてから会社作りで心掛けていることを教えてください。
漢那さん:会社の姿勢としては、新しいものを作るっていうのを大事にしてきました。例えば、新規で事業や物事を進めるときに、できないことが出てきて壁にぶつかった際、できない理由や仕組みを、できる仕組みに変えてきたっていうのがあります。できる仕組みさえ作っていれば難しいことでも対応できるようになるので。ただ、この新しいことに取り組んで結果を出すってことがほんとに大変で、頑張って行かなきゃって思うんですけど、こういう辛い経験をすればするほど、これはできるできないの判断がつくようになるし、商品作りはマラソンと一緒だから走り続けないとダメだよね。って思いますね。

—「商品作りはマラソンと一緒」わかりやすい表現ですね。現在出している商品は種類がとても豊富に感じられますが、商品作りはどのように考えておられるのでしょうか?
飲んでみて、自分たちが好きかどうか。それが社内の基本スタンス
漢那さん:種類の多さに関しては、お客さんがいろんなものを求めているからそのニーズに沿ったものを提供しているという形ですね。我々は石垣島に住んでいるので、一番日本で競争条件が悪いと思っています。その中でうちのお酒をどう選んでもらうか。考えた時に、県外の人が求めているだろうものを作って楽しんでもらうことだと思っています。また、社内の基本スタンスとして、自分たちが美味しいと思うものを作っています。自分たちが好きな味なら他の誰かも好きなはずだと。そういう思いで作っています。
—お客さんのニーズを理解しながら、たくさんの商品を生み出してこられたのですね。今回はそんな魅力的な商品の中から、IMUGE.に着目してお話を伺えればと思います。IMUGE.が生まれた経緯について教えてください。
昔は当たり前のように飲まれていた芋酒
漢那さん:はい。IMUGE.は、100年前までは沖縄でも普通に飲まれていたんですが、やがて消えていった芋酒になります。沖縄の人が日常的に飲んでいたお酒で、それをIMUGE.として復活させました。沖縄ではお米が取れないので、お酒をまともに作ることはできず、本州と違って米が主食ではなくさつまいもが主食でした。なのでお酒自体も芋を使っているお酒が流通していたんです。さつまいもを主食として食べ、その余剰分を酒にする。それが当時の人の唯一の楽しみでした。
—なぜ消えていったのでしょうか?
漢那さん:明治維新が起こった時から、家庭でお酒を作る場合でも税金を払わなければいけなくなったんです。その時に酒造りを事業化すれば消えていなかったのかもしれませんが、事業化まで発展するところはなく、徐々に消えていってしまいました。そこで、歴史的背景が強い沖縄の原料を使ったお酒ということで私たちが復活させることにしたんです。

—そのような歴史的背景があって生まれたのですね。では、IMUGE.の商品としての魅力について教えてください。
漢那さん:ジャンルとしては、焼酎でも泡盛でもなく、スピリッツになります。原料には黒糖が入っていて味は芋焼酎と黒糖焼酎を合わせたような感じです。それぞれの特徴として、黒糖焼酎は最初に甘みがきて、後味はスッキリ、芋焼酎は飲み込んだときに鼻から抜ける芋臭さがあります。IMUGE.はその両方を持っているので、アルコールをそんなに感じないお酒に仕上がっています。お客さんからも飲みやすいお酒だとよく言われますね。
—芋焼酎と黒糖焼酎の良いところだけを持っているお酒なのですね。歴史的背景の強いお酒を復活させたのもそうですが、地元・石垣島に対する思いを教えてください。
伝統は守るものではなく、伝統を使って新しいものを作ること
漢那さん:地元でやっていくのが当たり前だと思っているので、石垣島に対する思いは前提としてあります。技術は日々進歩しているので、味だけ伝統のままというのは誰も求めていないものです。伝統っていうのは守るものじゃないから、伝統は使って作っていかないといけないと思っています。地元のニーズに沿ったものを作って新しい伝統が生まれるんだとそういう考えでお酒は作っていますし、地元に対してはそういった思いがあります。
—では最後に、これからのビジョンについて教えてください。
漢那さん:今長期で目指しているのは、地元産を増やした商品を作りたいと考えています。地域の農業に貢献していこうって思いがあるので、農業もやっていて、来年からは芋けんぴを出そうと思っているので、酒造りと農業とダブルでやっていこうと思っています。5年後、10年後でいうと、世界中に商品を売り出して海外進出をしていきたいですね。ようやく、自分たちの技術が海外に通用するだろうなという感触も得てきているので、世界中を目指して、夢は大きく、まずは先進国に全部届けたいです。
—海外進出も成功する未来が見える気がします。是非ともその夢を実現させたいですね。本日はありがとうございました。

編集後記
漢那さんの会社経営の考え方、酒造りへの思いが熱く、とても濃密なインタビューとなりました。特に伝統の捉え方で、伝統を継承するためには、古い伝統をそのまま継承するのではなく、進歩した技術を利用して新しいものに作り変えるというスタンスで酒造りをされていて、そうした思いがIMUGE.にも込められているのだと思いました。今回は多くの種類の中から芋酒・IMUGE.に着目してお話を伺いましたが、オンラインストアにはまだまだ魅力的な商品が並んでいます。新しいお酒を探している方は、ぜひこの機会にオンラインストアを覗いてみてください。
ご紹介
Profile

請福酒造有限会社
社長