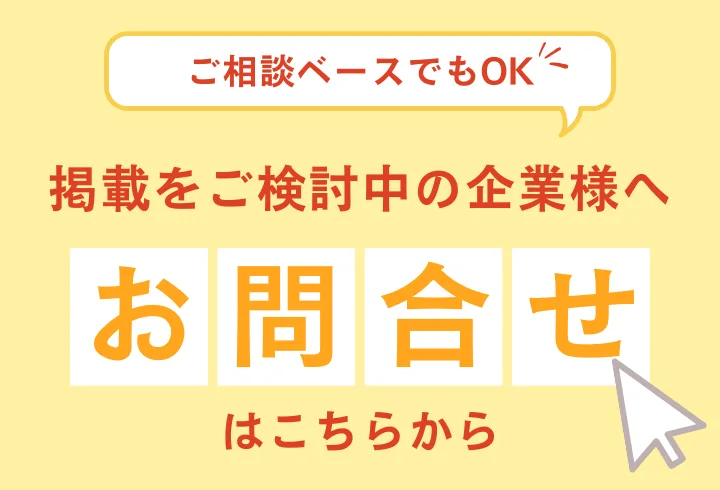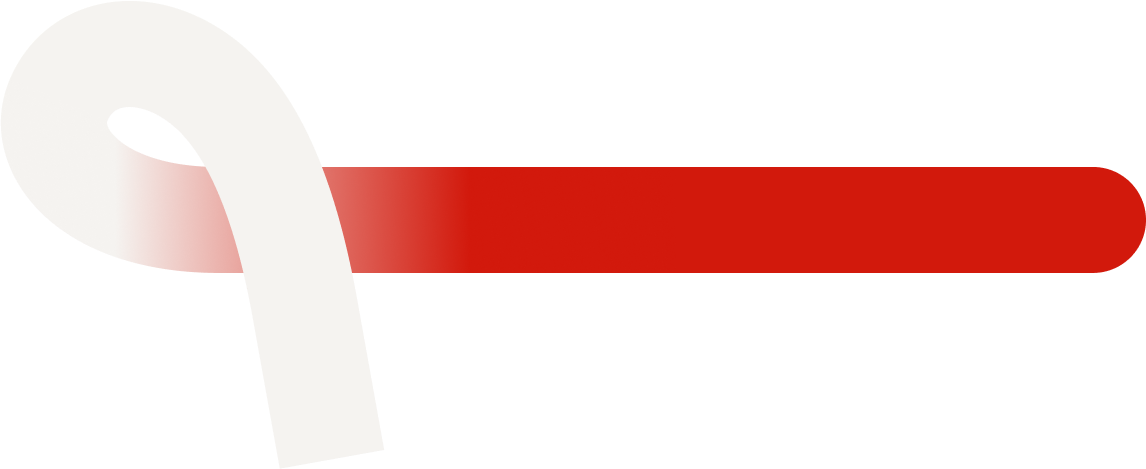近年、Web広告の効果は右肩下がりと言われています。クリック率や制約率の低下、広告コストの上昇…。多くの企業が「以前のように成果が出ない」と頭を抱えています。
では、この変化の中でどうすれば広告効果を高められるのでしょうか。
今回の記事では、株式会社ウェブリカ代表・石塚直樹とCHRO・梅村周平による対談から、“対談動画を広告に活用する戦略”について解説します。
広告に「スルー力」が働く時代
石塚
「最近はWeb広告運用そのものが難しくなっています。広告枠は限られているのに、出稿したい企業は増え続けている。結果、費用は上がるのに成果は下がる構造になっているんです。」
梅村
「確かにSNSを見ていても、広告に反応しなくなりました。昔は“あ、広告だ”と驚いてクリックすることもありましたけど、今は自然とスルーしてしまう。」
石塚
「そうなんです。ユーザーに“スルー力”が身についてしまった。クリック率も制約率も下がっているのはそのせいです。」
梅村
「つまり、広告を見る側の“慣れ”が成果を落としているんですね。」
石塚
「ええ。だからこそ、今の広告運用で成果を出すには、別の視点が必要なんです。」
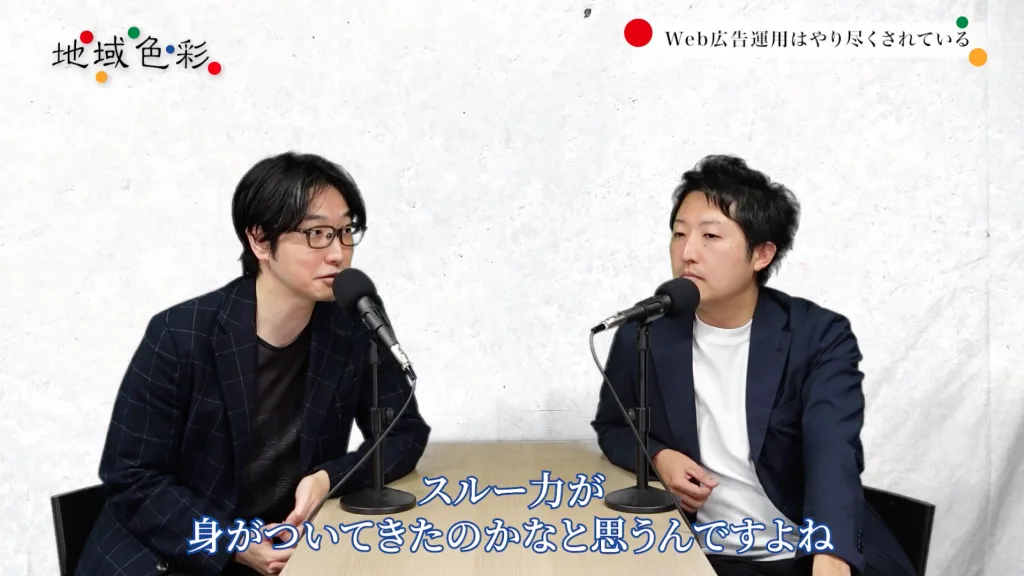
勝負を分けるのは“クリエイティブ”
梅村
「じゃあ、変えるべきは広告の媒体や設定ではなく…?」
石塚
「そうです。結局は“クリエイティブ”です。ユーザーに響く表現を作れるかどうかが最大のポイントになります。」
梅村
「例えば、従来よくある自撮り動画+テロップの広告もありますよね。」
石塚
「はい。ただ、あれだと『広告が出てきたな』とすぐ分かってしまう。結果的にスルーされやすいんです。」
梅村
「確かに、“広告らしさ”が強いと、見る前に戻してしまうことが多いです。」
石塚
「そこで私たちが注目しているのが“対談形式”のクリエイティブです。自然な会話を広告にしたほうが反応が取れるんです。」
梅村
「広告っぽくない広告、というわけですね。」
音声と動画を活用した新しい対談形式の広告
梅村
「なぜ対談形式だと効果があるんでしょうか?」
石塚
「今はTikTokやInstagramのおかげで“音声付きで動画を流し見する文化”が広がっています。だから“誰かが話している動画”は広告として違和感なく受け入れられるんです。」
梅村
「確かに、文字だけのバナーよりも、声や表情がある方がリアルに伝わりますよね。」
石塚
「その通りです。広告の役割も“注意を引く”から“必要だと感じてもらう”に変わってきている。会話形式なら、その瞬間を自然に作れるんです。」
梅村
「じゃあ広告の目的自体が変わってきている、と。」
石塚
「ええ。広告はただ目を引くだけでなく、ユーザーに『これは自分に必要だ』と思わせるクリエイティブへ進化しないといけません。」
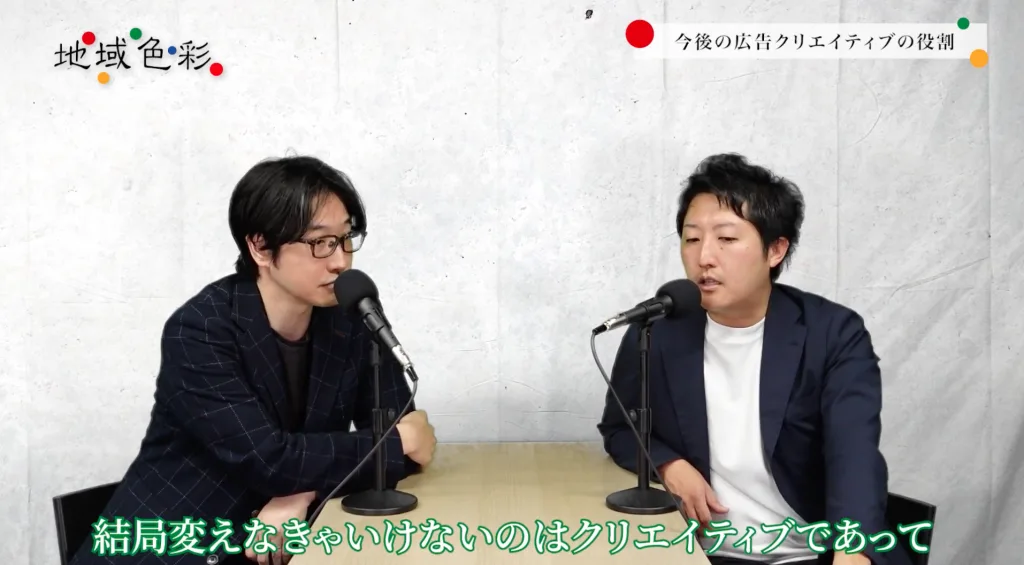
切り抜き+ABテストで磨く
梅村
「実際にどう広告として使うんですか?」
石塚
「収録した対談動画を切り抜いて60秒程度に編集します。そのとき『自分なら反応するな』と思うワードを意識的に入れる。そして複数パターンを作りABテストするんです。」
梅村
「なるほど。数字で一番響く表現を選べるわけですね。」
石塚
「はい。勘やセンスだけでなく、データで勝負できるのが強みです。」
梅村
「じゃあ僕の発言も切り抜かれて広告になる可能性があるんですね。」
石塚
「もちろんです。いいフレーズがあれば、そのまま広告で活かせますよ。」
広告と検索をつなげる導線
梅村
「広告を見ても、その場でクリックしない人も多いですよね。」
石塚
「そうなんです。でも実は“後から検索する”人が多いんです。問題は静止画バナーだと検索行動に繋がらないこと。」
梅村
「なるほど。じゃあ動画の方が有利なんですね。」
石塚
「はい。対談動画をYouTubeに公開しておけば、広告を見て気になった人が検索から本編にたどり着ける。これで“反応しなかった層”も回収できるんです。」
梅村
「広告とコンテンツが連動する仕組みになるわけですね。」
石塚
「そうです。1本の収録から広告とコンテンツの両方を作れる。一石二鳥の方法です。」

まとめ
今回の対談から見えてきたのは、広告効果が下がる時代だからこそ「人の言葉」「自然な会話形式」が武器になるということです。
ラジオ対談形式の動画は、広告としてもコンテンツとしても活用でき、切り抜きとABテストで最適化し、さらに検索行動まで設計すれば成果を最大化できます。
ラジオ対談形式の動画広告について気になる方はこちらの動画をチェック!
次回予告
第3話では、「地方創生」という言葉の意味を改めて考えていきます。
ぜひ次回のコンテンツもご覧ください。
ご紹介
Profile