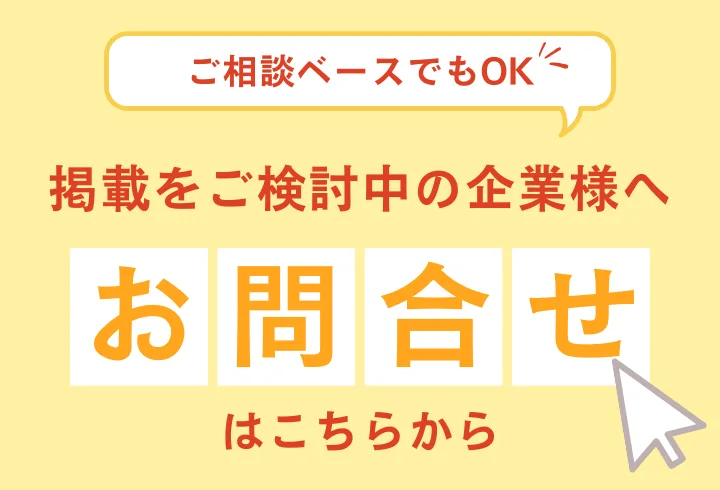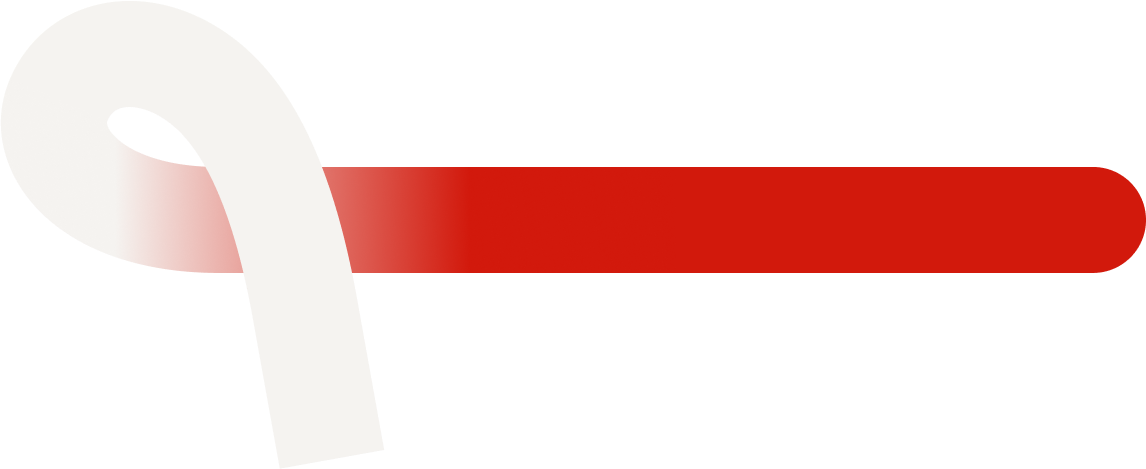「子育てこそ、いちばんクリエイティブな仕事だと思ったんです。」
そう語るのは、才能教育アカデミー 世田谷デザイン・代表の松田智子さん。
かつて三洋電機や日本ビクターなどでプロダクトデザイナーとして活躍し、グッドデザイン賞も受賞した経歴があります。
出産を機に第一線を離れた後、教育の世界へ転身。現在は東京都内で、子どもの創造力を引き出す美術教育に取り組んでいます。
デザインの本質を“考える力”と捉える松田さんの教育論には、AI時代を生きる子どもたちへの示唆が詰まっています。今回は松田さんの教育に対する想いとその実践についてお伺いしました。
目次
現場で磨いた「ユーザー視点」-プロダクトデザイナーとしての原点
石塚: まずはご経歴からお伺いしてもよろしいでしょうか?
松田: はい。もともとはインハウスのプロダクトデザイナーとして、三洋電機、日本ビクター、未来技術研究所などで製品デザインを担当していました。電子レンジやテレビ、ビデオデッキ、カーオーディオといった家電製品の外装デザインを手がけていました。
石塚: 家電のデザインというと、一般的にはなかなか意識されにくい分野ですよね。どのような観点で取り組んでいたのですか。
松田: 一番大切にしていたのは”驚きと感動のある新規性のあるデザイン”と“使う人の立場に立つこと”です。まず人が見て感動する様な新しいデザインである事が重要ですが、操作性や視認性、それを使う人がどんな新しい世界を体験できるかという”ライフスタイルのデザイン”まで含めて考えて行きます。
石塚:当時からユーザーの視点も意識されていたんですね。
松田: そうですね。実際にユーザーのご家庭を訪ね、使い勝手を観察することもありました。デザインの新規性だけが先行すると、かっこいいけれど一般の人には馴染みにくい製品になってしまう。その逆も然りで、そのバランスを取ることが難しくも楽しい部分でした。
“形だけではなくライフスタイルもデザインせよ”-グッドデザイン賞と師からの規範
石塚: 印象に残っている仕事や成果はありますか。
松田: 新人時代に一番最初に担当した電子レンジがグッドデザイン賞を受賞しました。その後もカーオーディオなどで受賞しています。形の美しさだけでなく、操作性や視認性、ライフスタイルについてなど、総合的な観点で評価される賞です。
石塚: まさにデザインの王道を歩まれてきたのですね。
松田: 大学時代の恩師の影響も大きいです。指導教授が日本インダストリアルデザイン協会の会長を務めており、「デザインとは形だけではなく、ライフスタイルもデザインすることだ」と教えられました。製品を通して人の暮らしを豊かにするという思想は、今の教育にもつながっています。
「子育ては最大のクリエイティブ」-現場から教育へ、軸はそのまま
石塚: その後、教育の道に進まれたきっかけを教えてください。
松田: 出産を機に第一線を離れました。当時は制度があっても女性がデザイナーとして継続するのは難しい時代でした。迷っていたとき、元デザイナーの父から「子育てこそ、いちばんクリエイティブな仕事だよ」と言われ、その言葉で気持ちが切り替わりました。
石塚: 素敵なお言葉ですね。
松田: 子どもを育てることは、まさに人間を創造する物凄く責任のあるクリエイティブな仕事だと感じました。三人の子どもを育てる中で、学びの環境をどう整えるかを真剣に考えるようになり色々勉強しました。ある日、娘の習い事のカルチャーセンターで展示されていた絵を見て、「ここで絵を教えることはできますか?」と尋ねたのが教育の始まりです。
石塚: その場で行動されたんですね。
松田: はい。履歴書と企画書を持ってくるよう言われ、そのまま講師として採用されました。最初はシニア向けのデッサン講座でしたが、皆さん熱心で、とても刺激的でした。

決めるのは子ども自身-個性を崩さず伸ばす“対話設計”の教室
石塚: 現在は子ども向けの教室を運営されていると思いますが、どのような特徴があるのでしょうか。
松田: 子ども自身が「何を描きたいか」を考えることを重視しています。こちらが見本を示すのではなく、「どんなものを描きたい?」「何を表現したい?」と対話しながら、アイデアを引き出します。描き方の技術指導はしますが、その子のタッチや世界観をできる限り崩さないようにしています。
石塚: 自由な発想を尊重するスタイルなんですね。
松田: そうです。多くの教室では先生の見本を真似する形が多いですが、うちは逆です。子どもが自分の意思で表現することが、考える力と自信につながります。最初は泣いていた子も、半年もすれば堂々と描き、意見を言えるようになるんですよ。
石塚: 絵を描くことが、思考のトレーニングにもなるのですね。
松田: ええ。画材も豊富に用意しています。100色以上の色鉛筆や、スポンジ・ローラーなども使います。学校の12色ではマッチしなかった感性を広げ、画材との“相性”を見つけることが大切です。

自由だけでは足りない、戦略だけでも育たない-“両輪”で出す結果
石塚: 生徒さんたちは数々の賞を受賞されていますね。
松田: ありがとうございます。特にMOA美術館の児童作品展には毎年出品しています。受賞作品を分析し、構図や色の傾向を研究します。たとえば夏開催なら空などの青系が映える、人物の表情や動きがあると評価されやすい、などの傾向です。
石塚: なるほど。かなり戦略的な指導ですね。
松田: そうですね。目的は受賞という目標に向かって一生懸命やり遂げる経験し、できるだけ賞を取って自信をつける事、本人も気が付かなかった高い能力に気が付かせる事です。3か月間の制作を通して、根気や集中力を養います。完成した作品には、子どもの熱意が宿っています。審査員がその“熱量”を感じ取るのだと思います。

“考えを形にする力”を育てる-未来を自分で設計できる人へ
石塚: 教え子さんの中には美術系の学校へ進学される方も多いのですか?
松田: はい。武蔵野美術大学や多摩美術大学などに進学した子もいます。ただ、私が目指しているのは“美術家を育てる”ことではありません。自分の考えを自信を持って表現できる人を育てたいのです。
石塚: それはまさに、社会で求められる力ですね。
松田: そう思います。現在は日本インダストリアルデザイン協会の正会員として、デザインスクール委員会にも参加しています。幼児から社会人まで、デザイン思考を広める活動です。教室の枠を越えて、「考える力」と「発想する力」を社会全体に広げたいと考えています。
石塚: 最後に、この記事を読んで興味を持った保護者の方にメッセージをお願いします。
松田: 才能を伸ばす第一歩は“環境づくり”です。親の役目は、子どもの芽を見逃さないこと。何が花開くかは分かりません。だからこそ多くの体験を与え、可能性を早く見つけてあげてほしい。もし私の力がお役に立てるなら嬉しいです。
編集後記
今回、印象に残ったのは、「見栄えの良さ」と「考える力」をどう両立させるか、という問いでした。短期的に“うまく見せる”指導は成果が早く見えます。一方で、松田さんが重視しているのは、子ども自身が題材を選び、試して、やり直す――そのプロセスを支えることです。どちらも一見「上手になる」ことに変わりはありませんが、持続性と自立というレンズで見ると意味は大きく異なるのだと感じました。
自由に任せるだけでも、勝ち筋だけを教えるだけでも足りません。個性を崩さずに、目的に応じた構図や色の戦略も伝える――松田さんの現場は、そのバランス設計が実務として機能しています。結果、受賞や進学といった可視化しやすい成果だけでなく、「自分で決めてやり切る」手応えが子どもに残っていきます。
AI時代において、「考えを形にする力」は生活にも仕事にも通用する基盤スキルです。今日“映える”表現を選ぶのか、明日も使える思考体力を育てるのか。保護者として私たちが日々の学びで選ぶたびに、子どもの未来への投資先が決まっていくのだと思います。
本稿が、家庭や学校での「教え方・支え方」を見直すきっかけになれば幸いです。

ご紹介
Profile

才能教育アカデミー世田谷デザイン
代表
三洋電機、日本ビクター、ケンウッド、未来技術研究所でプロダクトデザイナーとして活躍。
電子レンジやカーオーディオ、テレビなど幅広い製品の外装デザインを手がけ、グッドデザイン賞を複数受賞する。
出産を機に第一線を離れ、「子育てこそ最大のクリエイティブ」という理念のもと教育の道へ転身。東京都世田谷区を拠点に、子どもの創造力と発想力を育む美術・デザイン教育を行っている。
生徒一人ひとりの個性を尊重し、自ら考え表現する力を引き出す独自の指導方針を確立。教え子の中には美術大学や建築・デザイン分野に進学する生徒も多い。
日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)正会員としても活動し、幼児から社会人までを対象に「考えるデザイン教育」を広めている。

株式会社ウェブリカ
代表取締役
新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。
地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。