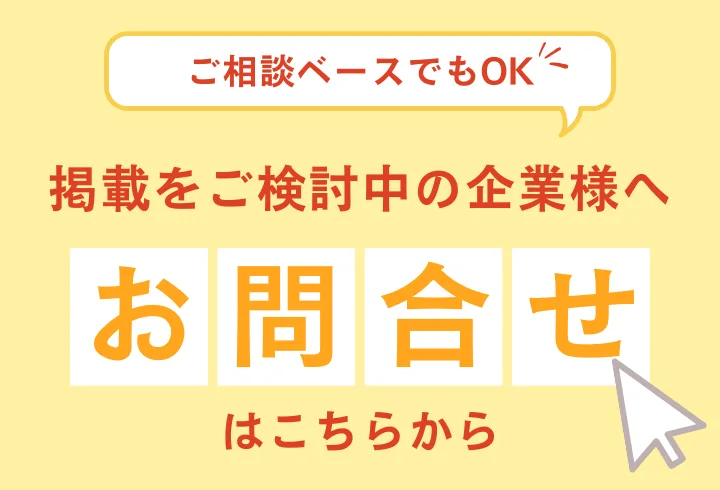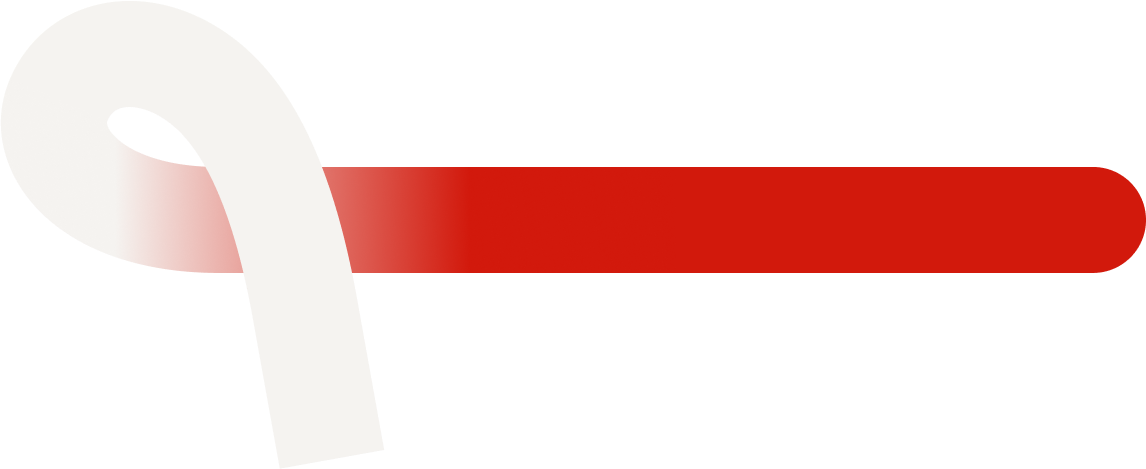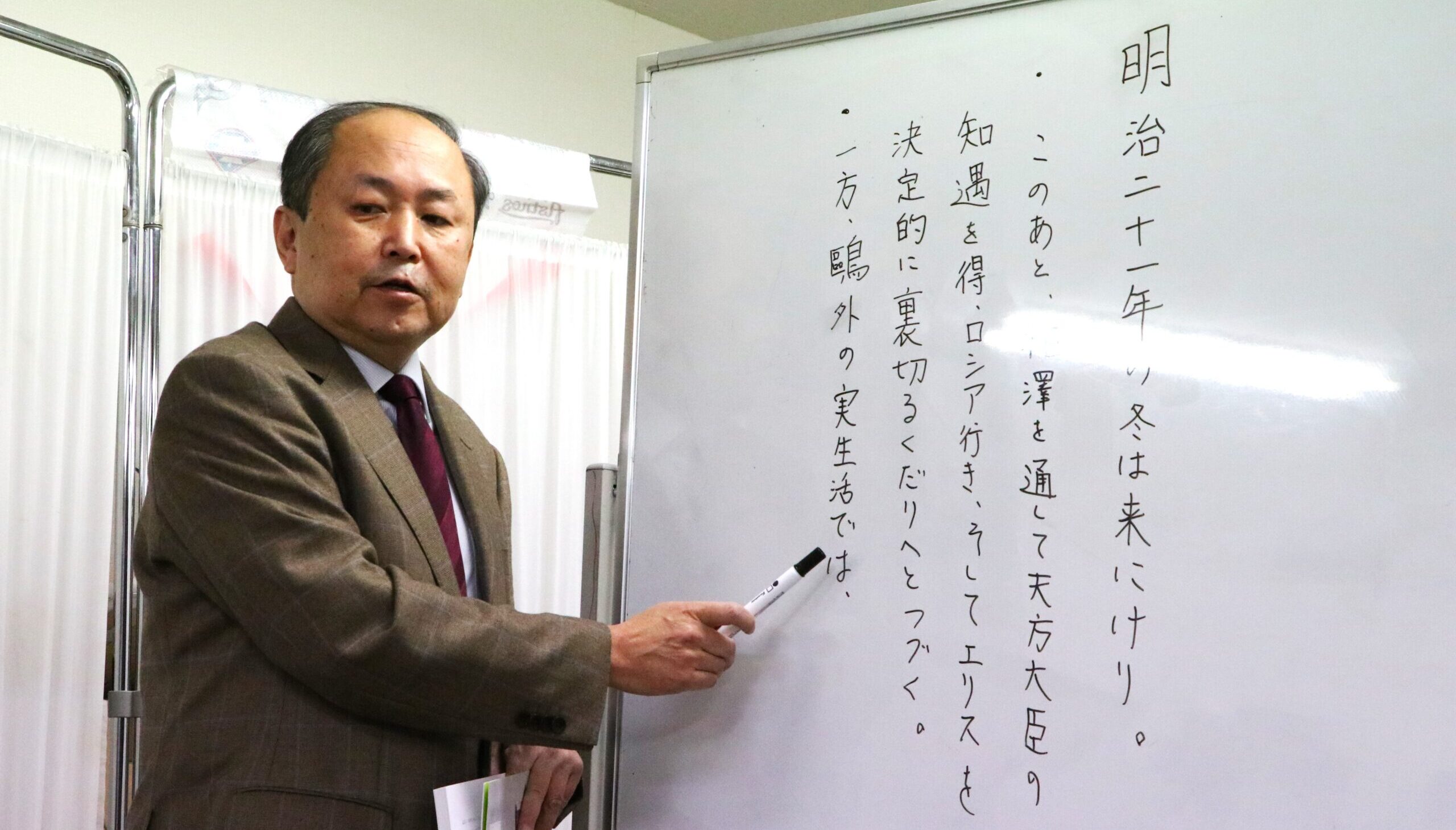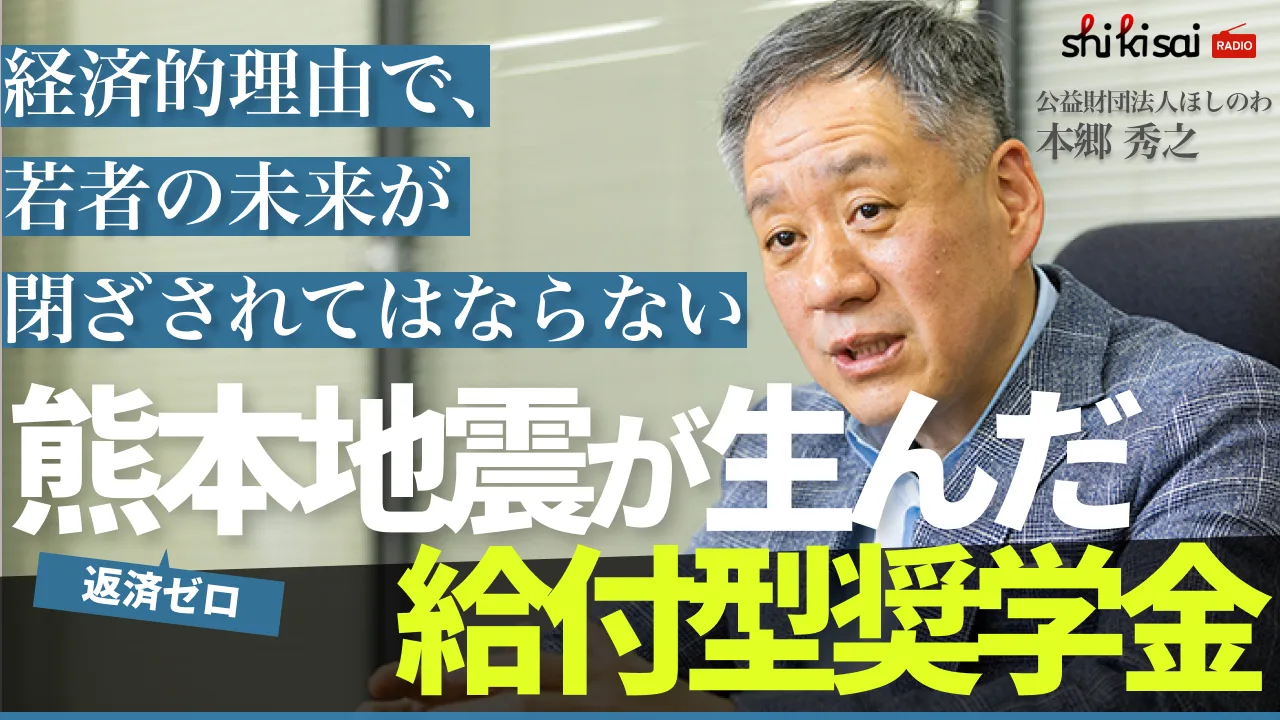公益法人制度は「世のため人のため」の活動を制度的に支える枠組みである。しかし、一般社団法人・一般財団法人から公益認定を取得するプロセスは複雑で、現場の審査運用には課題も残る。公益財団法人公益事業支援協会で主任研究室員を務める行政書士の横井俊祐さんは、弁護士・公認会計士・研究者らと専門チームを組み、「公益法人の設立の壁を低くする」ことに取り組む。本稿では、公益法人制度の要点、審査現場の実情、協会のサポート体制、認定成功の鍵、そして今後のビジョンについて伺った。
今回は石塚直樹がナビゲーターとなり、横井さんのキャリアと公益事業支援協会の取り組みについて伺いました。
目次
挑戦の原点――公益法人制度の概要
石塚:公益法人の設立支援をされているとのことですが、まず制度の概要を教えていただけますか。
横井さん:公益法人制度は、社会の公益に資する活動を制度的に支える仕組みです。一般社団法人または一般財団法人を設立し、その後に内閣府や都道府県へ公益認定申請を行う二段階の流れとなります。「1階(一般)」から「2階(公益)」へ上がるイメージです。
石塚:認定が難関と言われる理由はどこにありますか。
横井さん:年間の申請件数は約100件ほどですが、そのうち約4割が取り下げられています。申請書類の準備に加え、委員会での審査を経る必要があり、制度への理解と労力が求められます。
制度運用の課題――「壁」を生む構造
石塚:なぜ難易度が高くなるのでしょう。
横井さん:書類不備への指摘は当然として、運用現場で法律に基づかない行政指導が繰り返されるケースがあります。例えば、事務所の広さや常勤職員数、寄付者の資産証明の提示など、公益認定の本質に関係の薄い事項が求められることがあります。
石塚:政府方針と現場がズレている印象を受けます。
横井さん:政府は公益法人を増やしたい方向性を示していますが、審査事務局は他業務との兼務や人事異動が多く、ガイドライン運用の熟度にばらつきがあります。また、委員会は全国で約250名ですが、公益の実務に詳しい委員は少数です。
設立の背景――理念を制度に乗せるために
石塚:公益事業支援協会はどのように生まれたのですか。
横井さん:設立は2021年です。契機は、理事長の千賀(弁護士)が公益法人設立に関わる中で、制度理念は優れているのに運用のハードルが高い現実を強く感じたことでした。公益を志す団体の活動が、制度運用の不均一さによって妨げられる状況を変えたいという思いが原点です。
石塚:具体的な背景はありますか。
横井さん:千賀が関わった公益法人の認定では、同趣旨の質問が形を変えて繰り返されるなど、膨大な対応が求められました。理念と制度運用の落差に直面し、「壁を低くする」ための専門チームが必要だと考えたのです。
実務支援――無料相談から行政対応まで
石塚:協会の支援内容を教えてください。
横井さん:まず無料相談を行い、必要に応じて書類作成から行政対応までサポートします。審査過程で根拠の薄い要求が出た場合は、行政手続法に基づき根拠提示を求めることで対応します。申請者の事業目的を論理的に整理し、必要な資料に落とし込みます。公益認定を受けるまでは、無料で相談を受け付けます。
石塚:制度知識と実務が噛み合っている点が印象的です。
横井さん:制度趣旨に即して説明を尽くし、不必要な要求は明確に線引きします。専門家チームで支えることにより、申請者の負担を下げられます。
実績と成功の鍵――「正しい知識」と「熱意」
石塚:これまでの実績を教えてください。
横井さん:これまでに12件の公益認定を実現し、同規模の申請が進行中です。成功の鍵は二つあります。正しい知識と運用理解、そして申請者の熱意です。理念と事業の公益性が明確で、資料に適切に落とし込めれば、審査の納得度は高まります。
石塚:認定によるメリットも整理いただけますか。
横井さん:国からのお墨付きによる信用向上、税制優遇、寄付者側の税控除などがあります。寄付が集まりやすくなり、事業の継続性が高まります。
今後の展望――新たに「千の公益法人」を創り出す
石塚:今後の目標を伺えますか。
横井さん:理事長の名にちなみ、「千の公益法人」を社会に送り出すことを掲げています。公益法人は、政府予算と民間営利では対応しづらい領域を埋める存在です。地域や社会の課題を制度の中で実装し、多様な公益が循環する社会をつくりたいと考えています。
石塚:最後に、読者へメッセージをお願いします。
横井さん:「自分の志を社会の仕組みにする」という選択肢を持ってほしい。最初の一歩は相談からで構いません。お待ちしています。
編集後記
公益法人制度は、理念としてはまっすぐでありながら、制度運用の複雑さゆえに「挑戦者」が挫折する現実がある。横井さんの語る「正しい知識」と「熱意」は、その乖離を埋める最低条件だ。制度を理解する言語を持つことは、公益性を実装するための前提となる。一方で、理念を制度言語に翻訳し、根拠資料へ落とし込む作業は容易ではない。ここに専門家チームの意義がある。
公益法人は、行政の予算配分や企業活動では取りこぼされる領域を支える装置である。多様な公益活動が制度に乗り、多くの担い手が生まれることで、社会の受容力は高まる。「千の公益法人」という目標は象徴的だが、そこに込められたのは数以上に、制度を通じて志を可視化し、循環させるという思想である。
制度の壁を低くする営みは、公益活動の選択肢を広げ、社会の厚みを増すプロセスにほかならない。
ご紹介
Profile

公益財団法人 公益事業支援協会
主任研究室員/行政書士
公益財団法人 公益事業支援協会 主任研究室員/行政書士。
一般社団・一般財団から公益法人への移行支援を専門とし、制度設計、申請書類の整備、行政対応まで一貫して伴走する。
弁護士・公認会計士・研究者などとチームを組み、「公益法人設立の壁を低くする」ことをテーマに活動。申請者の志を制度に落とし込み、公益性の整理・事業構造の言語化を支援する。
これまでに教育・福祉・文化振興など多様な分野の公益認定に関与し、現場の声を制度運用へ接続する役割を担っている。

株式会社ウェブリカ
代表取締役
新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。
腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。
地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。