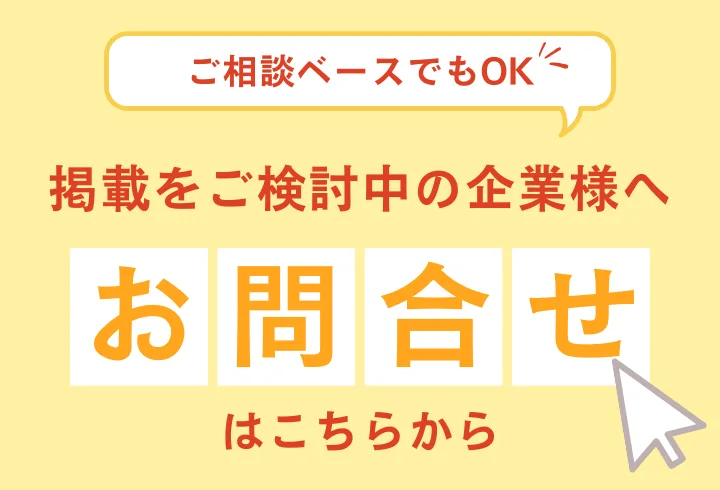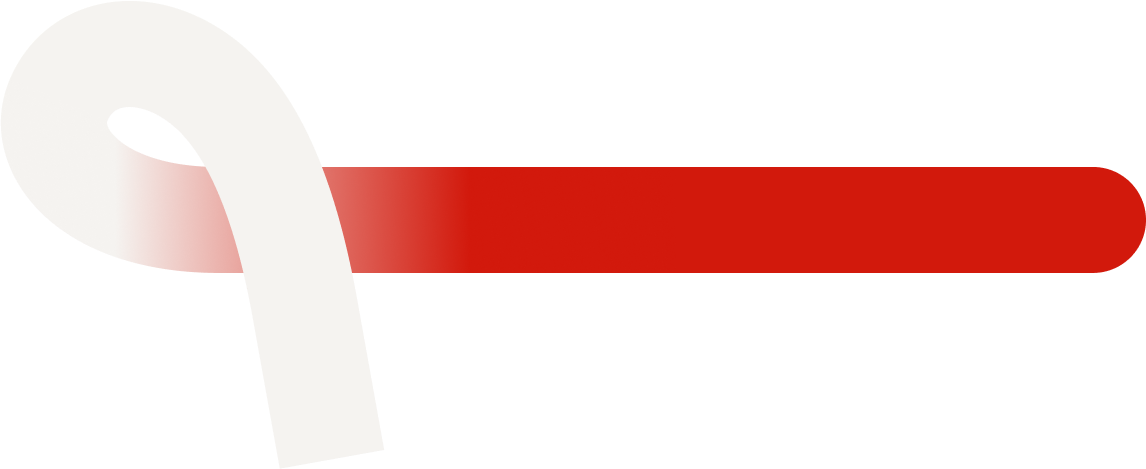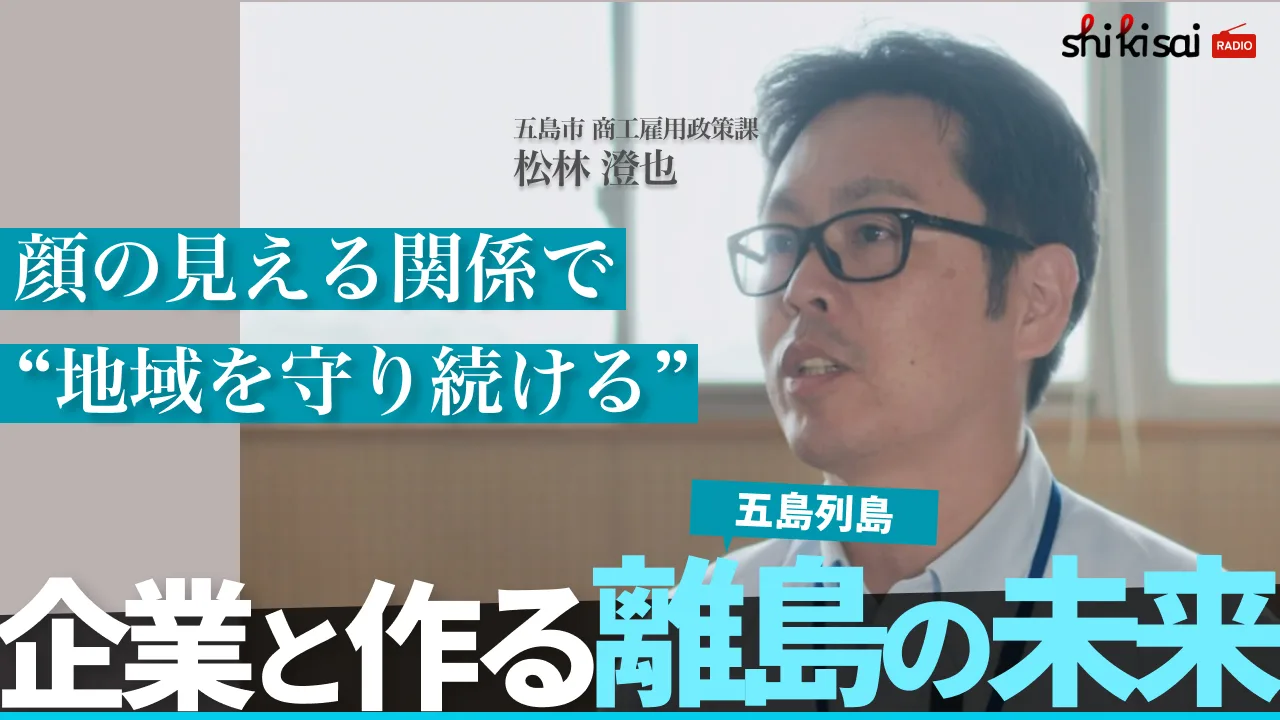目次
企業誘致の最前線から見る“持続可能なモノづくり都市”の現在地
「浜松は“やらまいか精神”のまちです」。そう語るのは、浜松市産業部企業立地推進課 誘致グループの川島さんと西妻さん。自動車、楽器、繊維といった産業に支えられてきたこの都市は、今も“挑戦のDNA”を基盤に次世代のモノづくりを牽引している。国内最大級の補助金制度やコンシェルジュ窓口の設置、スタートアップ誘致など、多面的な支援が功を奏し、令和6年度の立地件数は全国でも高水準の22件。浜松は今、産業イノベーションの都市として新たな局面を迎えている。
今回はウェブリカの石塚がナビゲーターとなり、浜松市産業部企業立地推進課 誘致グループの川島さん・西妻さんに、浜松市の企業誘致戦略とその背景にある理念について伺いました。
挑戦の原点──浜松が“モノづくりのまち”となった理由
石塚:
まず、浜松市を産業の観点から見るとどのような特徴があるのでしょうか。
川島さん:
浜松市は全国20の政令指定都市のひとつですが、県庁所在地ではなく、大都市圏にも隣接していません。それでも人口約80万人の都市に成長したのは、民間企業や産業の力によって発展してきたからです。歴史的には、自動車・楽器・繊維の三産業が基幹であり、現在でもスズキ、ヤマハ発動機、ホンダといった輸送機器メーカーが地域の中核を担っています。
石塚:
この地域に優れた企業が多い背景には、どんな文化的要素があるのでしょうか。
川島さん:
「やらまいか精神」と呼ばれる文化があります。“とりあえずやってみよう”という挑戦を重んじる気風で、まさにベンチャー精神の原型です。新しいことに積極的に取り組む姿勢が、地域全体の発展を支えてきたと思います。
産業構造の進化──次世代分野への挑戦
石塚:
現在の浜松市では、どのような分野を重点的に育成しているのでしょうか。
川島さん:
「はままつ産業イノベーション構想」というビジョンを掲げ、7つの成長分野を定めています。輸送機器分野ではEVやドローンといった次世代輸送用機器、加えてロボティクス、ヘルスケア、エネルギーなど、持続的発展に資する分野を強化しています。産業構造の変化に柔軟に対応し、地域産業全体の持続性を高めていきたいと考えています。
成果と仕組み──22件の誘致を支える「企業立地コンシェルジュ」
石塚:
浜松市の企業誘致は非常に成果を上げていますね。成功の要因はどこにあるのでしょうか。
西妻さん:
まず、浜松市自体が“モノづくりのまち”としてのブランドを確立し、企業にとっての安心感や信頼感を得ていることが大きいです。また、私たちの課では「企業立地コンシェルジュ窓口」を設置し、土地探しから許認可の手続き、補助金申請までをワンストップで支援しています。
石塚:
補助金制度も手厚いと伺いました。
西妻さん:
静岡県と浜松市合わせて土地代の25%補助(上限4億円)、新規雇用1人あたり100万円、建物・機械への10%補助と、全国でも最大級の支援水準です。実際に、補助制度が立地の決め手になったという企業も多いです。
立地と環境──“日本の真ん中”が生む物流と防災の優位性
石塚:
浜松市は立地的にも恵まれていますね。
西妻さん:
東京と大阪のちょうど中間に位置しており、東名・新東名の2本の高速道路が通っています。インターチェンジは10箇所以上あり、物流面で高い評価をいただいています。さらに、市有地として新たな産業用地「阿蔵山産業用地」を整備しており、災害リスクの低い高台に位置しています。BCP対策の観点でも有利です。
支援の広がり──行政・民間・地域が連携する誘致体制
石塚:
ソフト面での支援や地域の連携はいかがでしょうか。
川島さん:
市役所だけでなく、浜松商工会議所や浜松地域イノベーション推進機構といった支援機関と連携し、企業同士のマッチングや技術相談も行っています。地元の大手メーカーOBがアドバイザーとして関わっており、技術面でも高いレベルの支援体制を整えています。
石塚:
実際に誘致された企業の反応はいかがですか。
川島さん:
横浜から移転した企業では、「地元企業との打ち合わせが非常にスムーズ」「技術的な意思疎通が早い」と好評でした。浜松の企業文化が“話が通じるまち”を形成しているのだと思います。
次世代誘致──DXとスタートアップの集積へ
石塚:
製造業以外にも、スタートアップやICT企業の誘致も進めているそうですね。
川島さん:
はい。浜松には約4000社の製造業者がありますが、それを「市場」と捉えたDX企業の誘致が進んでいます。たとえば、在庫管理DXのエスマット、生産計画AIのスカイディスクなど、ICT企業の活動が広がっています。製造業とITが交わることで、地域全体の競争力が高まりつつあります。
人と暮らし「国土縮図型都市」に生きるワークライフバランス
石塚:
浜松は働きやすいまちとしても注目されています。生活環境の面はいかがですか。
西妻さん:
「都会と田舎のバランスがちょうどいいまち」です。中心市街地と自然が近く、通勤・生活・レジャーの距離が短い。終業後に海でサーフィンを楽しんで帰る人もいます。国土の縮図のような多様な環境が働く人のライフバランスを支えています。
地域課題と未来──“選ばれるまち”を目指して
石塚:
一方で若者の流出という課題もありますね。
川島さん:
大学進学を機に東京へ出る若者が多く、U・I・Jターンが課題です。そこで、市内の高校生・中学生に地域企業を知ってもらう教育連携を進めています。企業訪問や職業体験を通じて、「浜松で働く」ことへの意識を育む取り組みです。
西妻さん:
また、UIJターン促進部署や奨学金支援も整備しています。地元企業と理系人材をつなぐことで、“浜松で働くことが誇りになる環境”を作りたいと思っています。
展望─産業の持続性を支える誘致の戦略
石塚:
最後に、浜松市の企業誘致をどのように位置づけていますか。
西妻さん:
地方創生の中で“仕事”の充実を図ることが私たちの使命です。産業力を高め、浜松の魅力を向上させる企業を誘致すること。それが市全体の活力に繋がると考えています。
川島さん:
新しい風を取り入れながら、地域企業を支援する。双方の力で産業が盛り上がるまちを目指し、今後も戦略的に企業誘致を進めていきます。
編集後記
今回の取材で印象的だったのは、浜松の企業誘致が“制度”ではなく“哲学”として存在している点です。補助金や支援体制の整備はもちろん、その根底にあるのは「やらまいか精神」という挑戦文化でした。行政と企業、市民が共通の価値観を持ち、地域産業を次の世代に繋げようとする意志が随所に見えた。
また、行政が一歩引いて“伴走者”として企業を支える姿勢も浜松らしい。コンシェルジュ制度や移住コーディネーターといった細やかな仕組みは、単なる経済施策にとどまらず、“人と産業の共創”を体現している。ものづくりの歴史を土台に、DX・スタートアップの風が吹き込み、浜松は今、新しいステージに立っている。
ご紹介
Profile

浜松市 企業立地推進課 誘致グループ
主任
大学卒業後、浜松市役所に新卒入庁。
スポーツ振興課を経て、経済産業省 関東経済産業局に出向し、地域産業振興やコロナ禍の経済対策に従事。
現在は企業立地推進課にて、企業誘致や産業イノベーション推進の実務を担当。行政・民間双方の視点を持ち、浜松市の持続可能な産業基盤の形成に取り組んでいる。

浜松市 企業立地推進課 誘致グループ
主任
民間金融機関での勤務経験を経て、浜松市役所へ転職。
広聴広報課にて広報誌制作や市民意見の収集に携わった後、企業立地推進課に異動。企業誘致支援、補助制度設計、マッチング支援などを中心に担当。
行政の信頼性と金融業界で培った現場感を活かし、企業の浜松進出を丁寧に支援している。

株式会社ウェブリカ
代表取締役
新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。
腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。
地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。