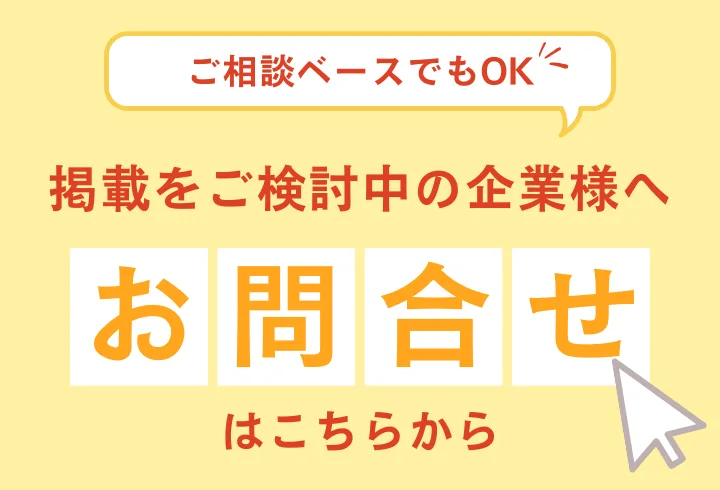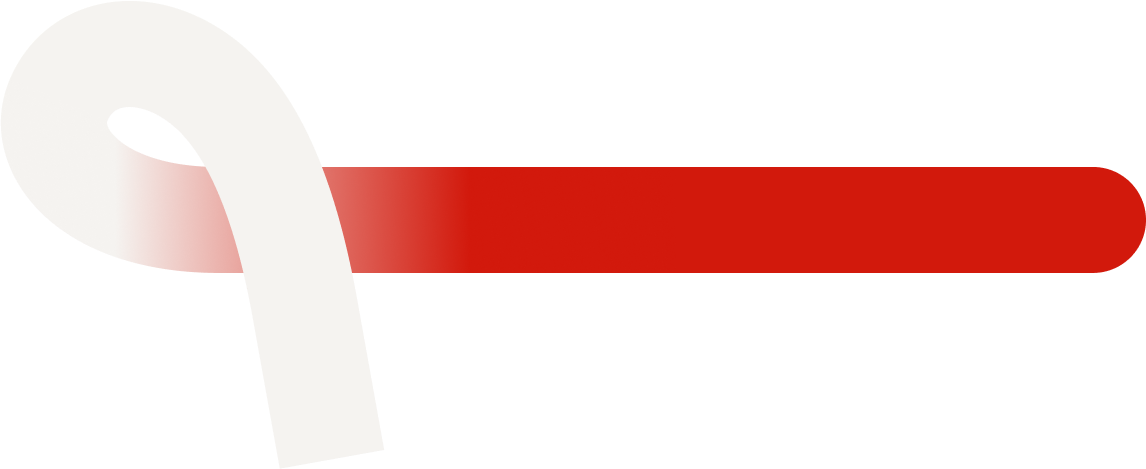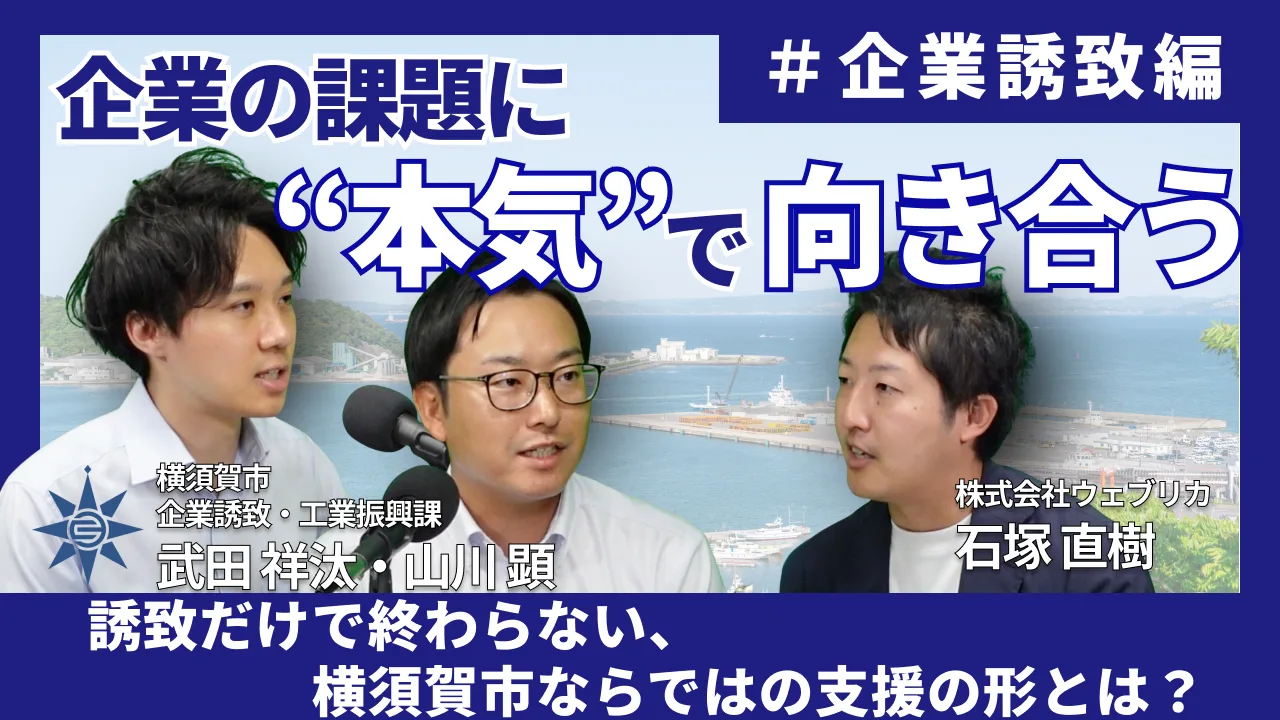“工業地域を工業で守る”。その言葉の裏には、制度と人、両輪の力が息づいている。相模原市が2005年に創設した企業支援制度「STEP50」は、全国でも稀な20年継続の仕組みとして、地域産業を支え続けてきた。制度の堅牢さの背後には、企業と行政の信頼がある。補助金という仕組みを超えて、「ともにまちをつくる関係性」をどう育んできたのか。本稿では、相模原市 副市長・奈良浩之さん、東栄電化工業株式会社 代表取締役・山本茂樹さんへの取材を通じて、“制度の力と人の信頼”が支える都市の姿を描く。
目次
ナビゲーター紹介
今回はShikisaiの石塚がナビゲーターとなり、相模原市 副市長・奈良浩之さん、東栄電化工業株式会社 代表取締役・山本茂樹さんに、産業と地域が共に発展するまちづくりの形について伺いました。
出会いが象徴する「行政と企業の信頼」
石塚:まず、お二人の出会いについて教えてください。
山本:きっかけは2004年頃のことです。弊社の裏手にあった2000坪の工場跡地が住宅地に変わるという話を聞き、驚いて市役所へ確認に行きました。工業地域に住宅が建つなんておかしいと思い、ほとんど“抗議”に近い気持ちで行。
その時対応してくださったのが奈良さんでした。非常に丁寧に制度の仕組みを説明してくださり、後日「住宅と共存できる工場づくりを進めましょう」と声をかけていただきました。そこから本格的に、工場の環境改善や移設に取り組み始めたんです。
奈良:私もよく覚えています。当時は都市計画の担当で、「工業地域なのに住宅が建つのか」という質問を多く受けていました。山本さんのように“声を上げてくれる人”がいたからこそ、行政としても課題に向き合うきっかけを得られたと思っています。そこから信頼関係が始まりました。
STEP50誕生──工業地域を守るという意思
石塚:そこから「STEP50」につながっていったのですね。
奈良:はい。平成17年に始まった「STEP50」は、まさに当時の課題意識から生まれました。工業地域でありながら住宅開発が進み、企業が操業しづらくなっていたんです。
工場跡地が住宅やマンションになると、後から来た住民の要望で企業が移転を迫られる。そんな“空洞化”の流れを止めるため、「工業地域を工業で守る」という方針を打ち出し、補助制度を設けました。
土地・建物への支援率は最大40%。新規立地だけでなく、市内企業の増設にも適用しています。20年にわたり、180件超の企業がこの制度を活用し、投資総額は2000億円を超えました。全国的にも類を見ない継続性です。
山本:私もその初期に利用しました。奈良さんから「STEP50を活用すれば、住宅地の中でも環境に配慮した工場がつくれる」と提案され、設備を刷新しました。結果的に、地域と共生できる工場に生まれ変わりました。
ものづくり都市・相模原の原点
石塚:相模原が“ものづくりのまち”として発展してきた背景には、どんな歴史があるのでしょうか。
奈良:ルーツは「軍都計画」です。昭和14年から24年にかけて、陸軍施設を中心に1668ヘクタールに及ぶ区画整理が行われました。今の碁盤目状の道路網は、その時の基盤です。
戦後は工場誘致条例(昭和30年)を制定し、製造業のまちとして発展しました。つまり、行政と産業が一体で育ってきた土地なんです。
山本:実際に、相模原は“都市と自然の中間”という理想的な立地です。アルミの表面処理を行う私たちのようなメーカーにとって、東京圏へのアクセスと落ち着いた環境の両方を兼ね備えている。ここで50年以上続けてこられた理由はそこにあります。
行政が「伴走者」であるということ
石塚:奈良さんは“企業に寄り添う行政”を重視されていますね。
奈良:制度を作るだけでは意味がありません。私たちは「企業の立場に立って動く」ことを徹底しています。ある経営者から「土地の値段ではなく、職員の姿勢で決めた」と言われた時、行政の本質を教えられました。
山本:奈良さんには当時、県の補助金制度も併用できるように翌日には一緒に県庁へ行ってもらいました。「この企業はこういう技術を持っている。支援してもらえないか」と、私たちの代弁者になってくれたんです。あれは行政というより“伴走者”でした。
奈良:今ではその姿勢が職員全体に浸透しています。かつては少数派だった「企業と並走する職員」が増え、20年続いたSTEP50の根幹を支えています。
工業地域の現在地──支える覚悟
石塚:近年、工業地域の維持にはどんな課題がありますか。
奈良:土地の確保が最大の課題です。企業からの問い合わせは多いのに、まとまった土地が少ない。だから職員には「現場を歩け」と伝えています。空き地を見つけたら登記簿を取り、所有者に手紙を送る。非常にアナログですが、地道に人の信頼を積み重ねるしかありません。
マンション開発が進む中で、「高く売れるなら住宅に」という流れもあります。でも私たちは、「ここは工業地域として残してください」と粘り強く伝えています。利益よりも“まちの未来”を見据えた判断を支援するのが行政の役目です。
山本:企業も同じです。土地を売れば利益は出ますが、地域や社員の暮らしを考えれば、ここに工場を残すほうが意味がある。住民との共存を重ねながら、ものづくりを続ける。それが私たちの責任だと思っています。
「ちょうどいいまち」相模原が描く未来
石塚:最後に、相模原で働く魅力について伺います。
山本:うちの社員の9割以上が相模原在住です。以前、火災を機に浜松への移転を検討しましたが、社員全員が「相模原で働きたい」と反対しました。通勤しやすく、自然も豊かで、共働きにも適している。生活と仕事の距離がちょうどいいんです。
奈良:人口動態を見ると、18〜22歳と60代が増えています。若者は大学が多く学びの機会に恵まれ、シニア層は“都会すぎず田舎すぎない”このまちに戻ってくる。相模原は「ちょうどいいまち」なんです。
圏央道の整備によって、東名・中央・関越・東北が高速でつながり、企業活動のハブとしての価値も高まっています。リニア中央新幹線の停車駅・橋本を中心に、新たなイノベーションが生まれる可能性も感じています。
山本:私たちも、相模原を開発と技術の“ハブ工場”として位置づけています。ここから新しい技術を発信し、地域と共に未来をつくっていきたい。
編集後記
相模原の強さは、信頼と制度の両方にある。行政が企業の声に寄り添う「人の力」と、それを長期的に支える「制度の設計力」。この二つが噛み合うことで、STEP50は単なる補助制度ではなく、“持続するまちの仕組み”として機能している。
奈良さんが語る「工業地域を工業で守る」という信念は、まちづくりを制度として支える骨格であり、山本さんが体現する「共存共栄の工場づくり」は、その理念を現場で生かす実践だ。
20年続く制度の背景には、数字では測れない信頼と覚悟がある。それは“政策”ではなく“文化”に近い。Shikisaiが見た相模原は、制度と人が同じ方向を向いて歩くまちだった。その歩みこそ、これからの地域経営の理想像である。
ご紹介
Profile

相模原市
副市長
相模原市 副市長。都市計画や産業振興分野を中心に、市政の中枢でまちづくり政策を牽引してきた。
2005年に企業支援制度「STEP50」を創設するなど、企業誘致と地域産業の活性化を制度面から支えてきた立役者の一人。
「工業地域を工業で守る」という信念のもと、補助金や税制支援にとどまらず、現場に足を運び企業の課題を共に解決する“伴走型行政”を実践している。
都市政策・土地利用・地域経営に関する豊富な知見を背景に、持続可能な産業基盤と市民生活の調和を追求。
制度の設計力と人への誠実な姿勢を兼ね備えた行政人として相模原のまちづくりを支えている。

東栄電化工業株式会社
代表取締役
アルミニウムの表面処理を専門とする技術系メーカーを率い、創業以来50年以上にわたり地域産業の発展に尽力してきた。 相模原に根を下ろし、「環境と共存する工場づくり」を掲げて経営を続けている。地域住民との対話を重ねながら、製造業が都市と調和して存在できるかたちを追求。技術への飽くなき探究心と、現場に寄り添う誠実な姿勢が信頼を生んでいる。人材育成や設備改善にも注力し、「企業は地域と共に生きる存在である」という信念のもと、相模原の“ものづくり文化”を次世代へと継承している。

株式会社ウェブリカ
代表取締役
新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。
腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。
地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。