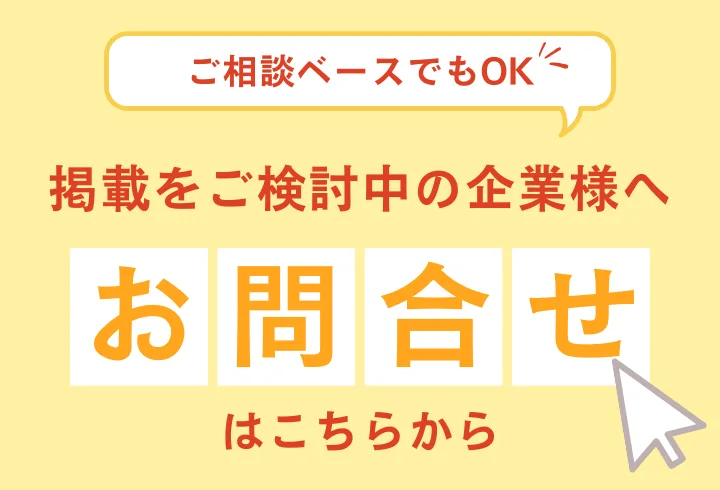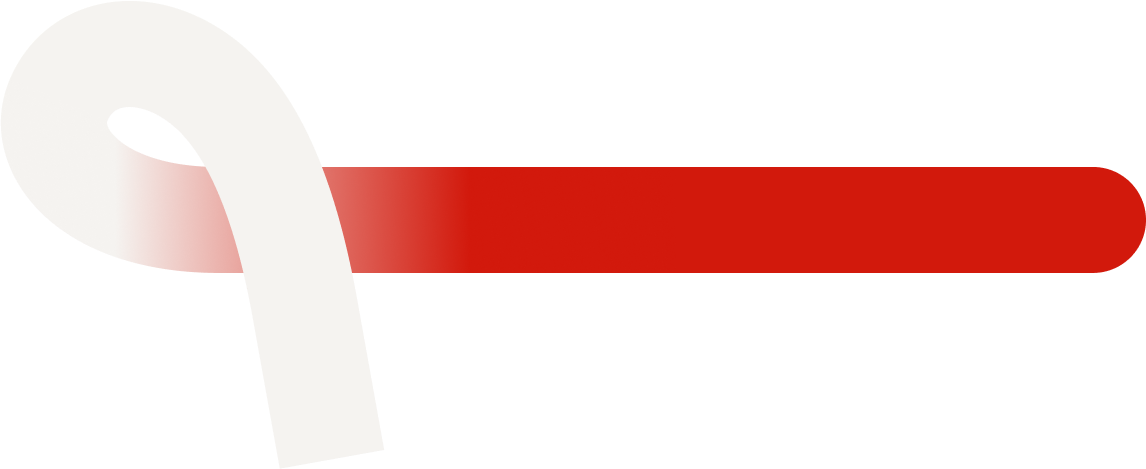「生きづらさを希望に変える」——京都市で活動する特定非営利活動法人ノンラベル。副理事長の田井啓太さんは、不登校や引きこもりの子どもを支援する母の姿をきっかけに福祉の道へ。自立訓練・就労継続支援B型・特定相談支援を備えた多機能型の福祉サービスを展開し、利用者一人ひとりの生活リズムの安定と社会との接続を丁寧に支えています。本記事では、設立の経緯、現場で大切にしている関わり方、地域とつなぐ就労体験、そして社会との「溝」を越えるための視点を伺いました。
目次
設立のきっかけは「家族会」から
石塚: まずは自己紹介と事業内容をお願いします。
田井: 京都市で福祉サービスを運営しているノンラベル副理事長の田井です。活動は今年で18年目になります。
石塚: 設立の経緯を教えてください。
田井: もともとは母(現・理事長)が立ち上げました。不登校や引きこもりの子どもを抱える親御さんが集う家族会から始まり、少人数のグループワークのような場が少しずつ広がって、現在の法人化につながりました。
石塚: ご家族の経験がきっかけに。
田井: はい。弟の不登校が最初の契機でした。長く家から出られない弟をどう支えられるか。同じ悩みを持つご家庭とつながる中で、共通項として発達特性への理解が必要だと気づき、支援の枠が形になっていきました。
田井啓太さんがノンラベルに関わるまで
石塚: 田井さんご自身は、いつ頃から?
田井: 私が入ったのは約15年前、設立から7〜8年が経った頃です。以前は全く別の仕事をしていましたが、転職のタイミングでノンラベルに加わりました。
石塚: 異業種からの転身ですね。
田井: 戸惑いもありました。ただ、母が積み上げてきた現場の知見と、地域に必要な支えを事業として継承したい思いが一致して、この道を選びました。
ノンラベルが提供する多機能型福祉サービス
石塚: 現在の提供サービスを教えてください。
田井: 自立訓練(生活訓練)、就労継続支援B型、特定相談支援の3事業です。いわゆる多機能型事業所として運営しています。
石塚: 利用者が多いのは?
田井: B型です。私たちは生活リズムの安定=働く準備の土台と捉えています。睡眠のリズム、入浴や食事などの生活の基礎が整うと、仕事を続ける力に直結します。
石塚: 利用者の課題にはどのような傾向がありますか。
田井: 対人面の難しさを抱える方が多いです。頭の中で「どう言えば相手に不快にならないか」を過剰に巡らせてしまい、反応が遅れる。結果として関わりが途切れやすくなる。診断の有無に関わらず、そうした生きづらさは少なくありません。
利用者に寄り添う「小さなコミュニケーション」
石塚: 現場ではどのように支えていますか。
田井: マニュアル化はしません。同じ時間を過ごし、会話の中で「今の言い方、とても良かったですね」とその場でフィードバックする。利用者同士の良い表現も拾い上げて肯定的に可視化します。小さな成功体験を積み重ね、経験値と自己効力感を育てるアプローチです。
石塚: 支援者側のスタンスは。
田井: 支援者自身が健康で、社会人として自然体であることが前提です。作った自分ではなく、買い物の失敗談や家の掃除の話など、生活者としての等身大を共有する。「この人も自分と同じ日常を生きている」と感じてもらえる関わりが、安心感を生みます。
地域とつなぐ就労体験の場づくり
石塚: ノンラベルの強みは?
田井: 施設外就労に力を入れています。家族が運営するコンビニエンスストアで、実際の職場体験や実践訓練ができる「安心して試せる場」を用意しています。
石塚: 自前で職場環境を整えているのですね。
田井: はい。既存企業への依頼だけでは、どうしてもマッチングの難しさが残ります。合わない経験を重ねてしまうと、本人にとって負担が大きい。そこで、まずは私たちが環境調整可能な場を用意して、ステップアップの土台にしています。
社会との「溝」を越えるために必要なこと
石塚: 長年の活動で感じる社会的な課題は。
田井: 社会で活躍する人々と利用者の間の「溝」です。良し悪しではなく文化の違い。まずは溝の存在を受け入れること。そして、診断の有無にかかわらず、誰しもが程度の差こそあれ生きづらさを抱えるという前提に立つことです。
石塚: 何から始めれば良いでしょう。
田井: 周囲に少しだけ配慮の視線を向けることです。職場の全員が常に元気でいられるわけではない。しんどい時に「大丈夫?」と言える関係性が、社会を少しずつ変えていくはずです。
石塚: 最後に読者へメッセージを。
田井: 私たちの活動は派手ではありません。でも、長く時間をともにしながら生きづらさを軽くする実践を積み上げています。まずは知ってもらうこと。それだけでも支えになります。地域で「試せる場」を一つひとつ増やしていきたいです。
編集後記
取材を通じて強く感じたのは、小さな日常の積み重ねが自立の土台になるということ。会話の一言を肯定し、良い表現をその場で言語化して返す。支援者もまた等身大の生活者として関わる。その連鎖が安心感と自己効力感を育み、社会への一歩へとつながっていく。
さらに、環境をつくる覚悟にも胸を打たれた。受け入れ先が少ないなら自分たちで整える。コンビニという生きた現場で、段階的に試し、失敗しても学べる安全網を用意する。これは支援を仕組みとして地域に実装する挑戦だ。
社会と利用者の間に「溝」があることを認める視点は、私たちの働き方や人間関係にも通じる。違いを前提に、互いのペースを尊重できる社会へ。ノンラベルの実践は、そのための具体的なヒントに満ちていた。
ご紹介
Profile

NPO法人ノンラベル
副理事長
「人の個性や生き方にラベルを貼らず、それぞれの可能性を引き出すこと」を理念に掲げ、地域や人の魅力を引き出す活動を展開。
学生時代から人と人とのつながりを大切にし、現在は多様な価値観を尊重する場づくりに力を注いでいます。
自身の経験をもとに、誰もが安心して自分らしく生きられる社会をつくることを目指し、教育・地域・ビジネスの現場で幅広く活躍。
これまで出会った多様な人々のストーリーを社会に伝え、次世代へとつなぐために奔走しています。

株式会社ウェブリカ
代表取締役
新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。
腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。
■編集長インタビュー
「メディア「地域色彩」立ち上げの背景とは?株式会社ウェブリカ・石塚直樹が語る地域企業活性化のビジョン」
https://chiiki-shikisai.com/webrica-ishizukanaoki/