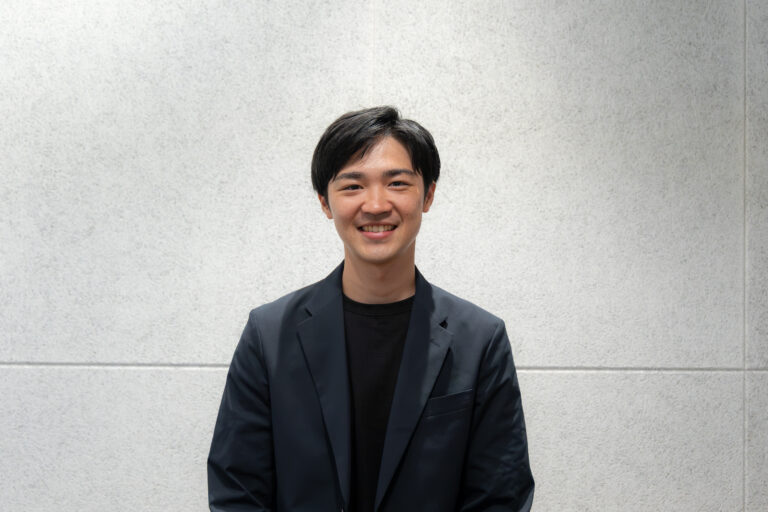今回は、LAND INSIGHT株式会社の代表取締役副社長・遠藤嵩大さんをゲストにお迎えし、全国の自治体と連携して進める宇宙衛星から受信する衛星データを活用した「圃場DX」プロジェクトについてお話を伺いました。少子高齢化と人手不足に悩む地域の農業行政を、どのようにテクノロジーで支えているのか。現場での信頼構築から、AI・衛星データを活用した課題解決のリアル、そして5〜10年後の地域DXの展望まで、じっくりと語っていただきました。
【第1章:なぜ圃場DXが必要だったのか?】
どんな課題から「圃場DX」は生まれたんですか?
遠藤副社長: きっかけは福島県南相馬市との出会いでした。農業や防災、林業など、行政のさまざまな担当者にヒアリングする中で、特に、農業行政における補助金交付のための現地調査である「転作確認」が負担になっているという声が目立ったんです。
南相馬市とは、どのように信頼関係を構築したのでしょうか?
遠藤副社長: 最初は本当に、何の目的もなく訪ねるところからでした。共同代表の藤田が知人経由で紹介してもらって、地元の方々と直接会話させていただいたり、地元の祭りに参加したりして(笑)。
そんなふうに通いながら話を聞くうちに、「私たちの技術が役に立てるかもしれない」と感じる地域の課題が見えてきました。
圃場調査のやり方に、どんな非効率があったのでしょうか?
遠藤副社長: 南相馬市では毎年300人が動員される現地確認。これまではシルバー人材センターに頼っていましたが、人員確保が年々難しくなっていたんです。しかも真夏の作業。高齢の方には過酷で、健康リスクも無視できません。
「じゃあ人手を使わずにできる方法は?」と考えたときに、衛星とAIの出番がやってきたわけです。

【第2章:衛星とAIで“見える”農業行政へ】
衛星データで作物を見分けるって、どうやっているんですか?
遠藤副社長: まず我々が行ったのは、現場の作業を実際に見に行くことでした。現地調査に同行して、何をどう見ているかを理解し、それをどう技術で置き換えるかを考えました。
実際の運用では、毎月1枚の衛星画像を取得して、過去の現地確認データをAIに学習させています。時期毎の色や変化のパターンから、どの作物が作られているかをAIが判別する仕組みです。
使用する衛星には、どんな特徴があるんですか?
遠藤副社長: 主に使っているのは10m解像度の光学衛星です。撮影された画像のうち月1枚ほどを使います。農地の変化を時系列で追えることが特徴です。
過去のデータをもとに、「この色なら大豆」「この変化なら水稲」といった学習ができるようにしています。
他のデータとの組み合わせも考えている?
遠藤副社長: もちろんです。解析の用途によっては、農業履歴や気象、土壌データとも統合していくことで、より精度を高めることができるかもしれません。しかし、農地に関わるデータのフォーマットや管理状況は自治体毎にバラバラであることが多いです。さらに、他の関連するデータは別の機関から取得する必要があり、データの統合利用へはハードルがあります。
今はアクセスできるデータを活用して、地道に整備を進めながら、モデル精度の改善に取り組んでいるところです。
【第3章:技術を届けるには“伴走”が必要】
自治体と協力するうえで、大切にしていることは?
遠藤副社長: 「現場に赴き、何がどう変わるか?」をちゃんと伝えることです。行政の方は、日々の実務にあたる中で現場感覚を重視されていると感じています。だからこそ、ウェブでの打ち合わせや、紙だけでの説明より、現場にも足を運び一緒に手順を確認する。その場で不安を一つずつ解消し、変化した後の姿を共有していくんです。
一方的な提案というよりは“伴走”。そういう姿勢が信頼と変化を生むと思っています。
このDXで、自治体の業務はどう変わるのでしょうか?
遠藤副社長: 現地確認が減れば、職員は庁舎に常駐できます。住民対応にも時間をかけられるし、農家さんの相談にも対面で丁寧に向き合えるようになる。
負担の大きな現地確認が、“地域農業支援のための対話”に置き換わっていく──それが一番の変化です。
地方の高齢化にも対応できる?
遠藤副社長: 圃場DXはまさにそのためのサービスです。やらなきゃいけない仕事は減らないのに、人手が足りない。これは日本の行政のあらゆる分野で起こっていることです。それを補うのがDXのひとつの役目だと考えています。
ただし「導入して終わり」ではなく、導入による変化によって、“誰の時間を、何のために、どう使うか”を意識した運用を構想し、実現していくことが大事だと思います。
【第4章:DXの先にある「地域の未来」】
農業以外にも応用できそうですか?
遠藤副社長: はい、森林管理、防災や土地管理の現場でも、現地業務を衛星データとAIで代替・支援できる可能性があります。
また、大手企業さんと協業して、我々の「現場感」を重視した課題発見とサービス開発のノウハウと、彼らの「技術力」を掛け合わせるような共創も広げたいです。
5〜10年後、地域のデータ活用はどうなっていると思いますか?
遠藤副社長: 今はまだ「紙をExcelにしただけ」の世界。でもこれからは、「どう使うか」から逆算してデータを整備するフェーズに入ると思っています。
公的データが標準化・共有化されれば、もっと柔軟で効果的な政策判断や事業連携ができるようになるはず。そこに向けて、我々もプレーヤーとして関わり続けたいと思っています。

編集後記
「圃場調査を、衛星とAIで。」──文字にするとたった一行ですが、その裏には「人手に頼り続けることへの限界」と、「生まれた余剰時間を、本来向き合うべき支援や対話に使っていく」という、地域に寄り添う強い意志があります。
技術と信頼関係、その両方を土台にした“足を運ぶDX”の挑戦は、これからの地域行政のあり方を照らすヒントになりそうです。