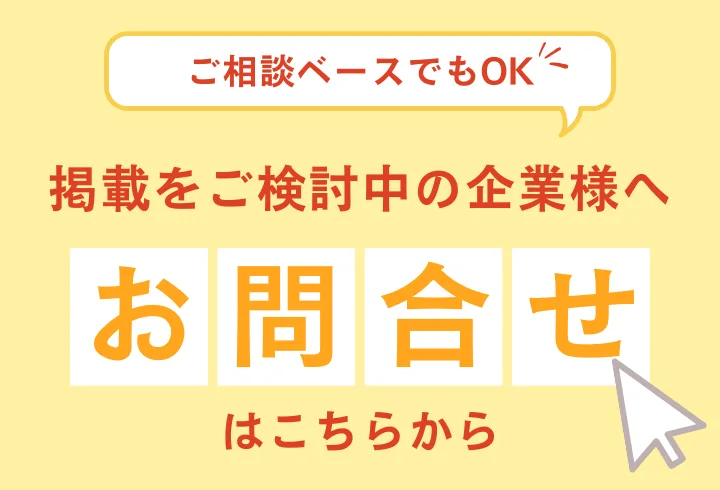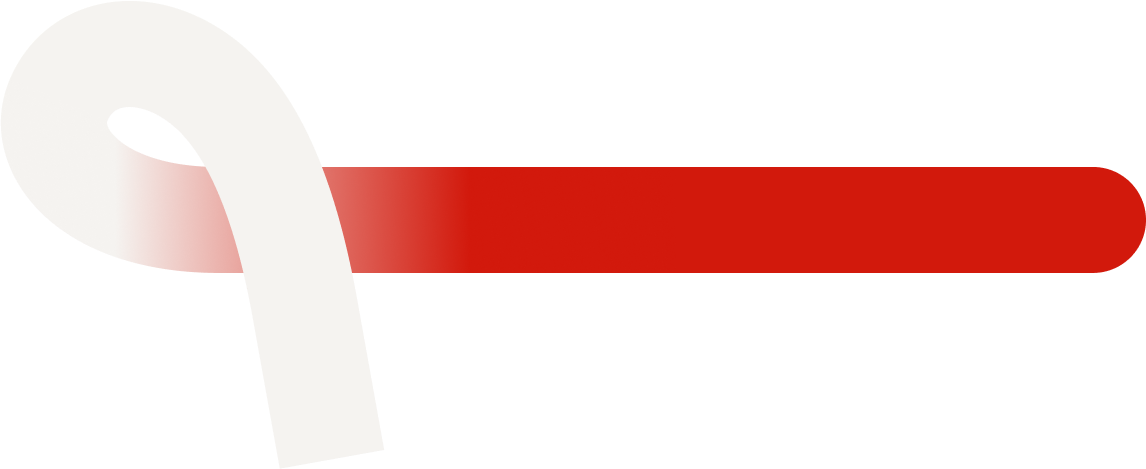タウリンは疲労回復だけじゃない! 大正製薬が語る研究85年と新たな発見

大正製薬株式会社
製剤第1研究室 室長
武井 拓人
TAKEI TAKUTO
タウリン――その名を聞けば「元気の源」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
しかし、その正体を正しく知る人は意外と少ないかもしれません。
大正製薬は戦前からこの成分に注目し、85年以上もの長きにわたって研究を積み重ねてきました。タコの煮汁から抽出していた時代を経て、医療の現場へ、そして今なお未知の可能性を探り続けています。
今回、長年タウリン研究に携わる武井氏に、その歴史と未来を伺いました。
目次
第1章:タウリン研究はどこから始まったのか?
――タウリンという名前は誰もが聞いたことがあるが、その実態を詳しく知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。
武井氏:大正製薬がタウリン研究を始めたのは、今から80年以上も前のことです。
――なぜ、そこまで早い時期にタウリンに注目したのでしょうか?
武井氏:会社の記録を調べると、1940年(昭和15年)頃からすでに研究を始めていたことがわかります。当時、タウリンは体の中に広く分布していることは知られていましたが、学問的にはほとんど解明されていませんでした。だからこそ「これは調べる価値がある」と考えたんです。
さらに、第二次世界大戦中には、海軍でパイロットや潜水艦乗組員の疲労軽減や視覚の補助に使われていたという記録も残っています。極限状態で働く兵士のパフォーマンスを維持するためにタウリンが利用されていたわけです。
このように、社会背景と研究者の好奇心が重なって、タウリン研究は大正製薬の中で大きく進み始めました。
第2章:研究を加速させた「再評価制度」
――そんな、タウリン研究に大きな転機が訪れたのはいつ頃でしょうか?
武井氏:1971年(昭和46年)に「医薬品の再評価制度」が始まったことが大きかったですね。それまで承認されていた成分を最新の基準で有効性・安全性を見直そう、という動きです。これを受けて、1960年代後半から社内でも薬理研究を本格化させました。
「タウリンは体にとって良さそうだ!」という感覚はあっても、科学的に説明できる部分はまだ少なかった。だからこそ、改めて徹底的に検証していこう、という機運が高まったのです。そこで社内研究だけでなく大学教授など社外の研究者と幅広い研究を行っていきました。
当時の大正製薬は、業界の中でもかなり先進的に研究に取り組んでいたといえると思います。

第3章:タコの煮汁から始まった挑戦
――研究初期のタウリンは、どのように手に入れていたのですか?
武井氏:今では合成によって良質なタウリンが安定的に作られますが、昔は社内でタコの煮汁から抽出していたんですよ。毎朝、大量のタコが会社に運び込まれ、社員が煮汁を扱っていたと聞いています。新入社員が「製薬会社に入ったはずなのに、まるで魚屋に来たみたいだ」と驚いた、というエピソードも残っています(笑)。
原料を確保すること自体が大きな課題でした。だからこそ、研究と同時に原料の製造にも挑戦していたわけです。これが、のちに化学合成技術を確立するための基盤になりました。
研究者の情熱と工夫が、現在の安定供給につながっているんです。
第4章:タウリンが持つさまざまな顔
――タウリンというと「疲労回復」というイメージが強いですが、それ以外にどんなことがわかってきたのでしょうか?
武井氏:タウリンの主な作用としては、「浸透圧の調整」「コレステロールの低下」「肝機能の機能向上」などが知られています。タウリンは心臓や肝臓、脳、網膜など、体のさまざまな場所に存在しているんです。体重60kgの人だと、なんと約60gものタウリンが体に含まれていると言われています。
特徴的なのは、体の状態に合わせてバランスを整える働きです。調子が乱れたときに、それを安定させる方向に作用すると考えられています。
最新の研究では、筋力維持や免疫機能、加齢に伴う変化など、多方面で有用性があることが示唆されてきました。
――食べ物からも摂れるのですか?
武井氏:はい。牡蠣やブリ、ホタテ、ホッキ貝、タコなどの魚介類に多く含まれています。一方で野菜にはほとんど含まれていないので、菜食中心の食生活だと不足しやすいかもしれません。現代は魚を食べる機会が減っているので、どうやって日常に取り入れていくかが課題ですね。
第5章:数十年をかけて社会に届いた研究
――研究が社会に届いた瞬間について教えてください。
武井氏:1980年代にタウリンが医療用医薬品として認められたことは、大きな出来事でした。肝機能や循環器系での効能・効果が評価され、臨床の現場で活用されるようになったのです。改めてタウリンのパワーを実感させられました。
ただ、ここに至るまでには長い年月がかかりました。研究着手が1940年頃ですから、40年以上をかけてようやく認められたことになります。データを積み重ね、国の基準と向き合い続けた先人たちの粘り強さが、道を切り開いたのです。
「研究者が世代を超えてバトンをつなぎ、社会に役立つ成果に結びつける」――この姿勢こそが、大正製薬の研究文化を物語っていると感じます。
第6章:これからのタウリン研究
――現代社会において、タウリン研究はどんな意味を持っているのでしょう?
武井氏:現代はストレスや高齢化など、これまでとは違う健康課題が増えています。タウリンはQOL(生活の質)の改善や健康寿命の延伸に貢献できる可能性があります。
さらに、タウリン単体だけでなく、他の成分と組み合わせる研究も進んでいます。たとえばタウリンに、アミノ酸の一種であるグリシンや特定の生薬の成分を組み合わせることで、睡眠の質改善につながる作用を発見しました。生活者の身近な悩みにどう応えられるか、新しい挑戦が広がっています。
――今後の挑戦をどのように描いていますか?
武井氏:これまで大正製薬はOTC医薬品を中心に研究してきましたが、今後は「予防」「未病」「治療」まで幅広く取り組んでいく必要があると思っています。社会の変化に合わせて、タウリンを軸にした新しい研究を展開し、生活者に還元していきたいですね。

編集後記
「タコの煮汁からタウリンを抽出していた」という驚きのエピソードから始まり、数十年を経て医療現場にまで活用されるようになったタウリン研究。そこには、先人たちの粘り強い努力と、未来を見据えた挑戦の積み重ねがありました。
タウリンは今もなお、解明されていない部分が多い成分です。しかし、それは同時に大きな可能性を秘めているということ。武井氏の言葉からは「未知に挑むことをやめない」という研究者の情熱が伝わってきました。
これから先、タウリン研究がどんな新しい健康の形を描き出すのか――その未来に、私たちも期待せずにはいられません…!
ご紹介
Profile

大正製薬株式会社
製剤第1研究室 室長
大正製薬にて長年リポビタンシリーズの研究開発に携わる