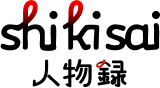ものづくりの世界へ飛び込んだ経緯を教えてください
ものづくりへの関心は、特別なきっかけがあったわけではありません。親がこの仕事をしていたことが自然な出発点でした。
ただ、小学生の頃の社会科見学では、博物館や美術館へ行くたびに自分の父の会社が関わった展示ケースを目の前にして「これはうちの父ちゃんの会社で作ったんだ」と誇らしく思った記憶が鮮明に残っています。その体験が、ものづくりに意識を向ける最初のきっかけだったのかもしれません。
大学卒業後は大手ディスプレイ会社に入社し、現場管理の立場から数多くの協力会社と共に仕事を進めました。自分の手で直接つくるのではなく、協力社や職人さん達に動いてもらいながら全体をまとめる仕事です。その経験を通じて「自分一人では成り立たない。周囲に生かされている存在なのだ」と学びました。スポーツで培ったチームワークの感覚と重なり、信頼関係や感謝の言葉の大切さを強く意識するようになったことが、現在の経営につながっています。
経営理念と「心豊かな人」を育てる場作り
経営理念に掲げているのは「心豊かな人を育てられる会社になる」という言葉です。単に仕事をするのではなく、仲間たちと共に悩んだり協力し合ったりすることで社員が成長し、誇りを持てる環境を整えることこそ会社の存在意義だと考えています。
私は社員に対して「自分さえ良ければいい」という考えを捨て、協力し合うことの大切さを繰り返し伝えています。その根底には「ありがとう」「ごめんなさい」「教えてください」といった言葉を素直に言える関係性が欠かせません。そうした日常の積み重ねが、責任感や自分を誇れる仕事につながっていくのです。
創業から50年以上が経ち、今は会社の制度や仕組みを一度壊して見直す取り組みを進めています。ベテラン社員には「僕らは次の世代の礎になる」と伝え、若い世代が30年先まで活躍できる基盤を残すことを自らの集大成と位置づけています。
経営の中で印象に残っているストーリー
現場で多忙を極めていた頃、忙しさに流されて人への接し方が雑になり、結果として物事がうまくいかない経験をしました。その反省から「眼光紙背に徹す」という合言葉を社内に掲げています。紙の裏が透けるほどよく見てよく考える。忙しいときほど丁寧さを忘れない。この姿勢を社員と共有することで、効率や成果が自然と高まっていくのです。
また、お客様への対応でも「どうしたいですか?」と直接尋ねるのではなく、まずは展示物や文化財への思いを語っていただきます。その思いを丁寧に受け止めた上でいくつかの提案を示し、一緒に選んでもらう。こうしたプロセスを経ることで、お客様自身が「共につくりあげた」と実感でき、満足度の高い結果につながります。
事業の魅力とお客様からの評価
私たちが手がけるのは博物館や美術館に欠かせない展示ケースです。展示ケース自体は脇役であり、できれば存在を意識されないほうが理想です。しかし、文化財や美術品を「守りながら見せる」ことは欠かせない役割であり、その使命に誇りを持っています。
例えばトヨタ博物館で手がけたミニカー展示では、子どもたちがガラスに手や顔を押し付けて夢中になる姿を想定して設計しました。実際、ガラス掃除は大変だと館側から言われましたが、それこそが狙い通り。展示を通じて心を動かすことこそ、私たちの仕事の本質です。
お客様からは「思っていた以上の展示が実現できた」という声を多くいただきます。傾聴と提案を重ねる姿勢が高い評価につながっているのだと感じています。

今後のビジョンについて教えてください
未来について明確な新規事業テーマを掲げているわけではありません。私たちは「守る世代」としての役割を果たす時期にあり、次の世代が「攻める世代」として挑戦できる環境を残すことが使命だと考えています。
若い世代に期待するのは「やり抜く力」と「自分で考える力」です。失敗やトラブルを恐れず、そこから学び成長してほしい。そのために評価制度も減点方式ではなく、「どうなりたいか」を共に考える仕組みに変えています。私が大切にしているのは、仕事を通じて人が育ち、心が豊かになっていく循環です。人が育てば組織も育ち、結果として良い仕事が生まれます。良い仕事は信頼を呼び、自然と新たな機会や成果につながっていきます。
だからこそ、目先の利益だけを追うのではなく、まずは人と心を大切にすることが何より重要だと考えています。
「お金を追えば逃げる。心を大切にすれば自然と仕事はついてくる。」
この信念を胸に、細見工業はこれからも人と文化を豊かに、そして、自分で自分を褒められるものづくりを続けてまいります。